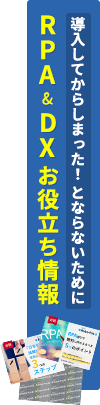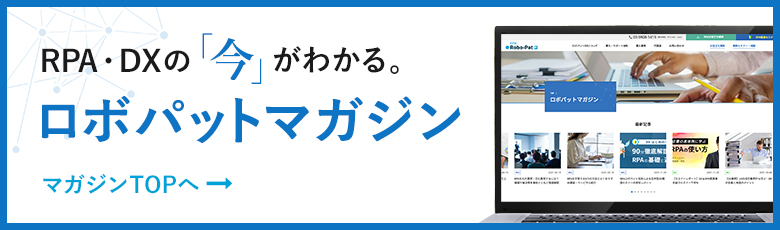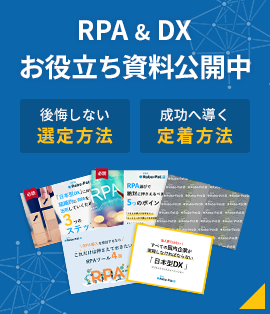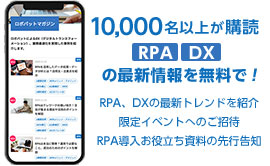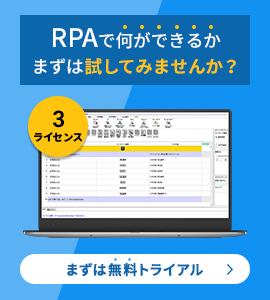RPAとは
RPAとは、「Robotic Process Automation」の略で、主にホワイトカラーにおける定型作業を自動化するソフトウェアロボットのことです。事務作業の中には、「勤怠管理」や「発注書内容の確認・データ入力」「データを集計し、表やグラフを作成する」など、ルーティン化されている定型業務が多数存在します。
こうしたルーティン化された定型業務に適しているのが、RPAのた技術です。ソフトウェアロボットに、代行してほしい内容を事前に設定しておくと、自動で指示通りに実行してくれます。
近年は、人手不足や働き方改革の動きが活発です。そこで大企業だけでなく、中小企業でもRPAの導入が進んでおり、注目度の高い自動化システムがRPAとなっています。
RPAでできること
RPAを導入することで、あらゆる作業を自動化することができます。ここからは、より具体的にRPAでできることをご紹介します。
データ入力
RPAでできることの1つ目は、データ入力の自動化です。データ入力は作業コストがかかる上、人的ミスが起こりやすい業務でもあります。RPAを導入すれば、入力作業を自動化し、作業時間の圧縮とミスの防止を実現できるでしょう。
データ集計
RPAでできることの2つ目は、データ集計です。膨大なデータを集計するには、かなりの時間と手間がかかります。しかし、RPAを導入すれば短時間でデータを集計することが可能です。集計時に起こりやすい入力ミスや操作ミスも防げるため、人的ミスのリスクの回避にも役立つでしょう。
データの収集・分析
RPAでできることの3つ目は、データの収集・分析です。あらかじめ欲しいデータの条件を設定しておけば、自動でデータの収集や分析をおこなうことができます。
勤怠管理
RPAでできることの4つ目は、勤怠管理です。従業員の勤務時間の計算はもちろん、打刻漏れや休日申請の処理なども自動でおこなうことができます。
請求書業務
RPAでできることの5つ目は、請求書業務です。事前に指示を設定しておけば、自動的に会計システムから請求データをダウンロードし、クライアントごとのフォーマットに合わせて請求書を作成することができます。
問い合わせ対応
RPAでできることの6つ目は、問い合わせ対応です。問い合わせの内容ごとに、適切な対応方法を設定しておけば、自動で適切なメッセージを送ることができます。設定方法によっては、24時間対応することも可能です。
ベンダーのRPAツールを利用しよう
近年、少子高齢化や長時間労働の是正などを背景に、働き方改革が求められています。そこで、業務効率や生産性向上などの効果が期待できる、RPAに期待が寄せられているのです。新聞やビジネス誌でも日本企業におけるRPAの活用事例が取り上げられており、期待の高さがうかがえるでしょう。そんなRPAですが、プログラミングなくして成り立たないと考える方も多いと思います。
RPAはどのように導入すればよいのでしょうか。RPAの導入を検討されている方には、ベンダーのRPAツールが簡単につくれるおすすめです。ベンダーのRPAツールは、特にホワイトカラーの定型業務に適しています。
近年登場してきたRPAベンダーの提供するRPAツールは、操作方法が簡単で自動化を実施するコストを削減できるものもあります。プログラミングスキルを必要としない、簡単な操作で自動化できるRPAツールも登場しており、専門知識がなくても簡単につくれるので運用しやすいでしょう。このようなRPAツールは、フレームワーク(枠組み)ができているためです。
フレームワーク(枠組み)ができているツールを利用すると、このように簡単にRPAをつくれるので自動化が実現できます。
ベンダーのRPAツールは、GUIで比較的簡単に設定できるツールもあり、自社に合った自動化を実施しやすいのが特徴です。
現在RPAツールを提供しているベンダーは数十社近くあります。各RPAツールは機能や性能に特徴がありますので、自社にあったRPAツールを選定しましょう。
RPAツールが作業する場を「サーバー型」と「デスクトップ型」と「クラウド型」の3種類に分類することができ、それぞれのタイプにメリットとデメリットが存在します。
サーバー型
社内サーバーにデジタルレイバーが導入されているオンプレミス型のRPAを指します。
デスクトップ型
パソコンのデスクトップ上で動くオンプレミス型のRPAを指します。
クラウド型
クラウド型で動くRPAを指します。
RPAツール導入の手順
RPAツール導入の手順は大きく5つのステップで構成されます。ここでは各ステップでのポイントを解説していきましょう。
自社の課題を見つける
まずは普段自社で行なっている業務を可視化し、作業時間を数値化しましょう。そして、自社の課題を下記の業務に分類してみましょう。
転記業務
データをExcelやスプレッドシートに転記する
情報収集業務
インターネット上の情報を収集する(Webクローリング)
集計業務
データを集計し、分析資料を作成する
データチェック業務
データの確認(異常値チェック、同一値チェック)をする
資料作成・送付
定型文での報告を自動的にメールにまとめ、送付する
RPAの対象業務を決める
RPAに任せる仕事はそれぞれ向き、不向きがあります。いきなりRPAツールを導入するのではなく、事前に自動化したい業務を明確にし、簡単につくれるRPAを調べましょう。
- 事務作業など、定型的(ルーチン)が発生する業務(次、週次、月次、年次など周期的に発生する業務)
- 単純作業であり大量に処理する必要がある業務(大量データの入力業務)
- 手順がルール化されている業務
- パソコンのみで作業が完結する業務
上記の業務がRPA化との相性がよい傾向にあります。
一方、人間の頭で考える必要のある複雑な業務は、RPAは向きません。RPAの導入成功には、RPAに任せる対象業務の見極めが重要なポイントになります。
RPAのシナリオを作る
RPAツールを使ってシナリオを作成しましょう。最初は、自動化工程が少ないシナリオ作りから始めます。
自動化工程の少ないシナリオとは、繰り返しと分岐が少ない業務のことです。ここであげる分岐とは、シナリオのあるステップで、もし数値が5以上ならAに進む、4以下ならBに進むような工程を指します。
RPAの成功の秘訣は「スモールスタート」です。最初から大規模な自動化を行うと、シナリオの作成や運用にうまくいかなかったときに大きな手戻りが発生します。
小さな業務自動化を繰り返し、RPA化のコツをつかんでいきましょう。
試験的な導入と見直し
シナリオの作成が完了したら、サンプルとする作業内容を決めて試験的な導入を始めましょう。ここで稼働を繰り返し、細かな修正を重ねていきます。
RPAツールの稼働は、1回で成功することは少なく、途中でエラーが発生することや予期せぬアップデートでシナリオが止まってしまうことがあるので注意が必要です。
前提として「RPA=完璧ではない、エラーが発生したときは停止する」という考え方のもと、試験を実施するとよいでしょう。
おすすめのテスト方法は、
手順1.部分ごとにシナリオ実行する
手順2.シナリオを通しで実行する
手順3.本番データを使いシナリオを実行する
手順4.数日間シナリオを連続実行する
本格導入の1カ月から3カ月間は、途中でシナリオが停止することを想定しておくといいでしょう。不定期に実施されるシステムアップデートは、シナリオが停止する要因になりやすいです。
本格的な導入
試験導入後、稼働/テストと修正を繰り返します。エラーの発生が減り、自動化が実現できるレベルになったら本格導入の準備をしましょう。
また、本格導入前に一度やらなければいけないことがあります。それは、自動化の運用手順やルールをまとめることです。
まとめておくとよいルールの一例
- RPAツールを活用できる社員の作成レベルと権限のを管理する
- 本格導入後の運用でトラブルが発生したときの初期対応と連絡方法を決める
- 自動化プロセスのメンテナンス頻度を決める
作成したRPAの詳細が分かるドキュメントや、自動化する方法をまとめたマニュアルなどを用意しておくとよいでしょう。
RPA推進担当に業務が属人化しない、誰でも分かるドキュメントを作成と連絡体制を構築します。
RPAのドキュメントに記載しておいたほうがよい一例
使い方
- ツールのバージョン情報
- エラー情報
- トラブル発生時の連絡先
- シナリオの概要図
- シナリオ作成者の名前と連絡先
- RPAの適応範囲
- 使用上の注意
などです。
RPA化する準備ができたら、簡単につくれるといえど一連の流れとシナリオ作成にかかる工数、自動化前と後の業務効果を測定しましょう。
RPAのシナリオの作り方
RPAシナリオの作り方として、手順の可視化とブラッシュアップをしましょう。シナリオを作成するには、次のような手順で行います。
業務手順を書き出す
手順1.
自動化したい業務が決まったら、業務の流れを書き出しましょう。
この工程で対象業務に使用するデータの種類、アプリケーションは何を使っているのか、ファイルフォーマット違いなどをまとめます。
手順2.
書き出した後、RPAツールを使わない方法を検討しましょう。
手順の見直しで業務効率が改善できる場合、無理して自動化する必要はありません。
手順3.
常に発生しない例外的な業務が発生する場合、別途メモにまとめましょう。
また、この工程で業務を可視化したら、誰にでもできる業務の標準化を考えます。属人化すると、担当者が変わり引継ぎがうまくいかないときに、ブラックボックス化してしまう恐れがあるためです。
複数人で業務手順をブラッシュアップする
一人で業務手順を書き出しても、個人の癖や省略が発生する場合があります。無駄な工数や不足している手順がないかを複数人で確認して、シンプルでミスの起こらない業務手順をブラッシュアップし設計しましょう。
また、業務手順を確認すると、全ての工程を自動化することが難しい場合があります。
その場合は、自動化を実施する工程と人が作業する工程を組み合わせ、臨機応変に対応していきましょう。
RPAツールの選定ポイント
現在、ベンダーが提供しているRPAツールは多種多様で、一例をあげても以下のように多くの種類があります。
- UiPath
- WinActor
- ロボパットDX
- Automation Anywhere
- Blueprism
- BizRobo!
- コボット
- Robotic Crowd
- PINOKIO
- BizteX mike
- FULLTIME
- パトロールロボコン
- ロボット経理バンク
- RoboRobo
これらの中から最適なRPAツールを選ぶには、選び方のポイントを理解しておくことが重要です。
RPAツールの選定ポイントはいくつかあります。選定基準としては、ツールに搭載されている機能の種類、ライセンスを利用できる人数や台数、ライセンスにかかるコスト、ベンダーからのサポート体制などです。
自社の自動化を行う際、どの選定ポイントを優先するかあらかじめ決めておきましょう。
どこまでRPA化するか
RPAを導入する際は、どこまでRPA化するべきか決めることが大切です。ここでは、どこまでRPA化するかを考えるポイントを解説します。
RPAの得意、不得意の切り分けに注意する
RPAは、ルーティンワークや定型業務を自動化するのは得意ですが、急な仕様変更が生じる業務や、紙媒体や手書きの文字・画像の認識は不得意です。すべてをRPAで自動化しようとしても、なか中にはRPAが不得意な業務も多いことを覚えておきましょう。
イレギュラー対応には人間が介入する
RPAは、さまざまな業務を自動化できます。想定外のトラブルが生じた際は、人間が介入する必要があります。RPA担当者が知識や経験が不十分だと、復旧に時間がかかるかもしれません。
対象業務に対して過不足のない機能のツールを選ぶ
近年、RPAツールは数多く登場しています。会計ソフト業務の自動化に特化したものや求人情報の管理に特化したものなど、それぞれ得意・不得意が存在するので、選定業務が自動化するのに十分な機能のツールを選定しましょう。
必要なRPAツールの機能を見極めるには、作業をフローチャートにまとめ、どのタイミングでどのような動作が必要かを整理することがポイントです。整理することでRPAツールの機能が必要ものか不要なものか判断しやすくなるでしょう。
サポートやメンテナンスを考えると有料ツールがおすすめ
RPA無料ツール(もしくRPAフリーソフト)は、RPAのお試しで導入したいときはおすすめです。しかし、実業務で自動化を実施しエラーやトラブルが発生したとき、慣れていないと対処に時間がかかります。
ベンダーが提供しているRPAツールの有料版は、サポートやメンテナンスフォローが含まれている場合が多くあります。エラー対応や困ったことが生じた場合を想定し、RPA有料ツールを利用することが望ましいです。
ベンダーが提供しているサポートとメンテナンスはそれぞれ異なるので、RPAツール選定する際に確認しましょう。
ITに関する専門知識がなくても扱えるツールが望ましい
プログラミングスキルがとわれるRPAツールは、カスタマイズ性と高度な機能が使用できますが、気軽に自動化したい方には向いていません。
シナリオを作成する際、【録画機能】が搭載されていたり、画面クリックでシナリオが作成できるRPAツールがおすすめです。特に初めてRPAを取り入れるRPA初級者は、特に直感的に操作できて簡単にRPAをつくれるツールを選ぶべきでしょう。
まとめ
この記事のポイントをまとめると次のようになります。
- ポイント1
RPAツールの選定は慎重に行いましょう。たとえば、「このRPAツールは自動化実績が多いから大丈夫だろう」と思っても自社に合ったRPAツールであるとは限りません。自社で実施する自動化のポイントを洗い出し、各ツールの特徴と適応しているか確認しましょう。
- ポイント2
RPAは完璧な技術ではありません。エラーが発生する可能性も考えましょう。シナリオを作成し、実行したら終わりではありません。本格導入後の対策もしっかり講じましょう。
もし、導入後にトラブルがあったら不安だという方は、サポートが充実しているRPAベンダーのツールがおすすめです。
RPAツール「Robo-PatDX(ロボパット DX)」では、業務診断会、スクリプト作成支援のほか、導入から実運用されるまでのサポート機能全般を無料で提供しています。
また、1カ月間PC3台分の無料トライアルもありますので、実際に動かしてみて自社に合っているか確認することができます。
RPA導入を検討されている際は、ぜひ「ロボパットDX」をご検討ください。