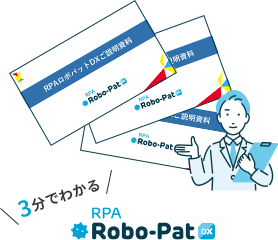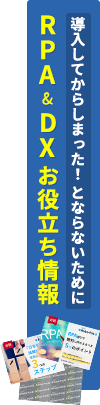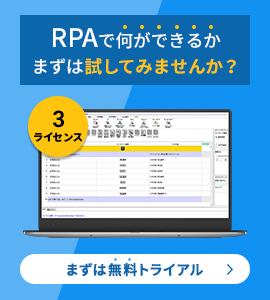デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?
デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital Transformation)を簡単に説明すると、「ITを活用して、企業組織やビジネスに変革を起こすこと」と言い表すことができます。そしてDXを推進する大きな目的のひとつが「企業の競争上の優位性を確立すること」です。
DXはスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって2004年に提唱されました。ストルターマン教授の定義では「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」としていますが、この概念だけでは企業やビジネスにDXをどのようにして活用していくか不鮮明でした。
その後、IT調査会社IDCによって、ビジネスの視点から見たDXは「企業が第3プラットフォーム(クラウド・ビッグデータ/アナリティクス・ソーシャル技術・モビリティー)技術を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデル、新しい関係を通じて価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」として明瞭に定義されました。
さらに、2018年12月に経済産業省がまとめた「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」の中では、
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。
この定義でDXはデータとデジタル技術を活用して、製品・サービスの変革は当然のことながら、企業の組織やビジネスの文化そのものまでを変革する必要性を示しています。
ここで注意すべき点はDXと「IT化」は異なるという点です。IT化はデジタルを活用して業務効率化を「目的」としているのに対して、DXはあくまでも情報化やデジタル化の推進は「手段」のひとつでしかないという点です。
DXの必要性
デジタル技術で新しいビジネスモデルを生み出す新規参入者によって、現代の企業間の競争はますます激しくなる傾向にあります。こうした中で企業が競争力を強化するためにDXの推進が求められていますが、国内におけるDXの必要性は、企業やビジネスのネガティブな要素を払拭する目的がその大部分を占めている現実があります。
ネガティブな要素というのは「2025年の崖」と「レガシーシステム」のことで、これらの要因はDXの推進を難しいものにしています。
DXが進まなかった場合に訪れる「2025年の崖」とは
2025年の崖とは、経済産業省が発信した、DXが推進されなかった場合に起こりうる国際経済競争の遅れや経済の頭打ちなどを表す言葉です。2025年までに起こるIT人材の引退とシステムのサポート終了によって引き起こされるとされており、克服できなければ、2025年以降に毎年最大12兆円の経済損失が生じる可能性があるとして警告しています。
経産省の報告によると、多くの経営者が将来の成長や競争力強化のためにDXの必要性について理解しているとされています。ところが、事業部門ごとに構築されたシステムや、過度なカスタマイズが施されたシステムは複雑化・ブラックボックス化しており、全社横断でデータの活用ができないなどの障害を抱えているため、DXがうまく進んでいない状況です。
さらに、経営層がDXの推進を望んでいたとしても、上記のような障害を解決するには業務自体の見直し、つまり経営改革が求められるケースが少なくありません。この場合、強引にDXを推進しようとしても現場サイドの抵抗は大きくなることは容易に想像され、いかにして円滑にDXを推進するかが課題になっています。
このようないくつかの原因がDX推進を停滞させ、2025年の崖で指摘されているさまざまなリスクに企業が直面することが予想されているのです。
レガシーシステムが抱える多くのリスク
2025年の崖で問題視されている老朽化や複雑化でブラックボック化した基幹システムのことを、「レガシーシステム」と呼びます。レガシーシステムが抱えるリスクの中でも2025年の崖の直接的要因とされているのが、「ブラックボックス化したレガシーシステム」です。これは、システムの内部構造がブラックボックスのように複雑化して、自社では修正できない状態にあることです。
この背景には、日本の多くの企業がシステム開発を社外ベンダーのITエンジニアに委ねてきたことがあります。システムのマネジメントをベンダーに委ねるということは、自社にシステムのノウハウが蓄積されないほか、レガシーシステムに貴重なコストやリソースが割かれ、新たなIT技術やデジタル技術などに投資が行われないということです。
また、レガシーシステムの保守・運用は属人的になりがちで、レガシーシステムの承継が困難であると回答した事業者は6割を超えています。これにより、2025年前後に訪れる有識者の退職によってシステムのノウハウは喪失してしまい、競争力が低下した多くの企業は事業機会を失ってしまう危機に直面するのです。
DXの推進がもたらすメリット
企業はDXを推進して2025年の崖とレガシーシステムのリスクという大きな課題に対応しなければなりません。ここまではDX推進をネガティブな問題を解決するための手段としてご紹介してきましたが、DX推進はあらゆるメリットを企業・ビジネスにもたらします。ここからは具体的なメリットについてご紹介します。
新しい価値を生み出す
DXの目的は企業・ビジネスが競争上の優位性を確立することです。つまりIT技術を活用することで他の企業にはない新しい価値を生み出せることがDX推進の大きなメリットのひとつです。
例えばシステム内のデータを社内横断で共有できるようになると、事業部門ごとでは掘り起こすことができていなかった価値を発掘し、新たな製品・サービスやビジネスモデルの開発につなげることが可能になります。
すでに、営業データをクラウド化、ビッグデータとして他部門と共有して活用し、分析によって得られた数値を営業戦略の指標とする動きは大企業を中心に活発になってきています。
また、AIを活用したビッグデータ構築も盛んになっており、自社製品と顧客のやり取りを解析して新たな顧客ニーズに対応するためなどに役立てられています。
生産性の向上につながる
DXがもたらすデジタル改革は、企業の「労働生産性」と「資本生産性」の双方を向上させます。DXの本質はあくまでも新しい価値を生み出して顧客とエンゲージすることですが、IT技術の活用によって生産性の向上や業務効率改善というメリットを得ることもできるのです。
働き方改革が求められている昨今は、どうしても労働生産性の改善を先に急ぎかちになっています。しかし、生産性を向上させるには資本生産性を向上させる取り組みに着手する方が重要です。
DXのデジタル変革によって経営改革を起こせば資本生産性の向上につながります。そして、IT化によって導入されたAIやOCR、そしてRPAなどによって業務効率が改善され、労働生産性の向上にもつながるのです。
労働生産性の向上の中でもクラウドを使った営業支援システムやRPAなどは導入の障害が少なく、成果が出るのも比較的早いことから現場レベルで導入が進んでいます。
日本におけるDXへの取組状況
2025年の崖対応やデジタル変革によるメリットを得られるDXの推進は、多くの企業の経営者層にとって課題・急務となっています。
株式会社電通デジタルが実施した「日本における企業のデジタルトランスフォーメーション調査(2019年度)」によれば、国内企業の約7割がDXに着手済みと回答しています。具体的なDXへの取り組みとしては、データ活用戦略の策定、組織やIT人材の開発・育成に注力するといった施策を展開しているようです。
しかし、諸外国と比較したときには国内企業のDX推進が遅れをとっているという状況にあります。スイスのビジネススクールIMDが発表した「デジタル競争ランキング」で日本は23位で、2位を獲得したシンガポールや10位の韓国と比較するとアジア圏の中でもかなり遅れをとっている結果です。
その結果、日本からはデジタルディスラプターが生まれていません。デジタルディスラプターとは、クラウドやAI、IoT、ビッグデータというようなデジタルテクノロジーを活用して、既存の業界の秩序やビジネスモデルを破壊するプレイヤーのことをいいます。
具体的には、デジタルの力でEC販売を変革したAmazonや、民泊という概念を変えたAirbnb、スマートフォンアプリでタクシーを利用できるようにしたUber、ストリーミングサービスで音楽の聞き方を変えたSpotifyなどが挙げられます。
デジタルディスラプターの多くはデジタルネイティブな新興企業です。新興企業であるからこそ、従来からのしがらみや縛りがありません。デジタル化が進んだ新時代に最適化したビジネスモデルで業界に参入することで、業界のシェアを奪っていきます。
このようなデジタルディスラプターが登場したことにより、そのプレイヤーが属する業界は大きく変革を遂げざるを得なくなっています。
しかし、日本からは目立ったデジタルディスラプターは登場していません。その理由は、レガシーシステムに起因するものだとされています。
また、日本でDXが進まない理由として、経営者層の知識・理解不足も挙げられています。CDO(最高デジタル責任者)が集まる団体、一般社団法人 CDO Club Japanの調査によると、「企業のデジタル改革が進まない理由」の回答のトップは「経営者層の知識・理解不足」でした。
近年、DXというキーワードは広く認知されてきており、多くの企業でもデジタルに対する取り組みが始まっています。しかし、経営層の理解がないままで進めるDXは成功しません。
このように日本のDXは諸外国とは異なる問題でデジタル改革の障害を抱えており、日本におけるDXは「日本型DX」として認識し推進していかなければなりません。
このまま日本国内の企業のDXが遅れてしまうと、日本企業は今以上に国際的なデジタル競走に取り残されてしまうことでしょう。
部署別に紹介!DXの取り入れ方
DXを推進するためには、部門ごとの業務変革から取り組むことをおすすめします。
特に、総務、経理、人事などの管理部門や営業部門は、DXを取り入れることで大きなメリットを得られる部署です。DX推進の第一歩として取り組むのに適しているでしょう。
管理部署の場合
管理に関する部署では、ペーパーレス化、RPA、テレワークというような業務効率化手法を導入することでDXを取り入れることができます。
ペーパーレス化
契約書や会議用資料をはじめとする紙の書類をPDFやPowerPointなどのデジタルデータに切り替えていくペーパーレス化も、DXへの取り組みの第一歩といえます。
ペーパーレス化は、全社で一斉にスタートしなくても部署や業務からでも始めることができます。紙の書類をなくすことで無駄な管理業務が減りますし、テレワークとも相性が良くなるため、業務効率が高まっていきます。
紙書類をデジタル化してくれる、ペーパーレス化代行サービスもあります。
RPA
デスクワークの中のルーチン化している定型業務を、ロボットに任せてしまうRPAも簡単に導入できるDXです。RPAを導入することで業務を効率化し、労働生産性を高められるほか、人材不足への対応などの効果を得られます。
ロボットで業務を自動化することで、ヒューマンエラーの防止につなげることもできます。
まずは最も成果につながりやすい部門にRPAを導入し、1部門で成果を生み出すことができたら、他部門あるいは会社全体へのRPA導入を考えていくと良いでしょう。
テレワーク
セキュリティ対策を施したパソコンをインターネット回線で接続して、場所や時間を問わずに働けるテレワークを取り入れる企業が増えています。
人口が減る日本において、介護や子育てなどと仕事を両立することができ、通勤に必要な移動時間が節約できるテレワークを導入するメリットは大きいといえます。
ペーパーレス化やRPAと同様に、まずは一部の部署や業務からでもテレワークをスタートできます。
営業部署の場合
営業部署では、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)、Web接客や自社Webサイトにチャットボットなどの業務効率化手法を活用することでDXを推進することができます。
SFAやCRM
それぞれの営業担当者の営業スキルや勘に頼って営業活動をおこなっているのであれば、SFAやCRMなどのシステムを導入することで大きな成果をあげられます。
SFAやCRMを活用することで営業以外の業務を楽にできるほか、売上を上げるのに最適な道筋へ導くことができます。
Web接客
Web接客とは、オンライン会議システムやチャットを活用して、Webサイトに訪れたお客様に対し、実店舗のスタッフと同じような営業や問い合わせ対応を行う接客方法です。
訪問営業の効果が出ていないというのであれば、取り組んでみてはいかがでしょうか。営業活動にオンライン会議ツールやメール、電話などを用いるインサイドセールス部隊の新設などもあわせて行うようにしましょう。
Webサイトにおけるチャットボットの利用
問い合わせ対応をコールセンターや個々の営業担当者だけに任せているのであれば、自社のWebサイトにチャットボットを取り入れてみましょう。Web接客とも相性が良く、FAQ(よくある質問とその答え)ページに記載しておけば、チャットボットに誘導することで顧客満足へとつなげられます。
商材にもよりますが、チャットボットを取り入れることで販売につなげられる可能性もあります。企業全体の売上向上と営業担当者の生産性向上、そしてコスト削減に貢献できる手法です。
DXへの第一歩をRPAで実現
では具体的にはどのようにしてDXを推進していけばよいのでしょうか。DXの推進は大きく3つの段階に分けて実行されます。
・第一段階:ITによる業務強化
・第二段階:ITによる業務自動化
・第三段階:ITと業務の一体化
第一段階の「ITによる業務強化」は旧来の基幹システムから脱却し、従来の業務を効率化させて生産性向上を図る段階です。
第二段階の「ITによる業務自動化」は、RPAなどのICTを活用して業務の自動化などでさらなる生産性向上を目指します。
そして、第三段階の「ITと業務の一体化」では、ITと現場がシームレスにつながった状態で、早いサイクルで新たな価値を創出する業務を遂行できるようにします。
「RPA(Robotic Process Automation)」は、DX推進の第二段階の「業務の自動化」で中核を担うツールです。さらには、第一段階においてもRPAは書類のデータ化など、既存のビジネス資源のデータ化業務を自動化する役割も果たすため、RPAはDXを推進する3段階のうち2段階の業務をカバーすることが可能です。
そのため、RPAはDXを推進する起爆剤として期待され、大小問わずあらゆる企業において導入が進んでいます。
RPAの特徴
RPAはホワイトカラーの業務を自動化して生産性を向上させるツールです。RPAの特徴は、人の手よりも正確に速く業務を自動処理する点です。
RPAは定められたルールがある単純作業の自動化において性能を発揮します。RPAによって人の手から単純作業が離れることは、人的リソースを他の業務に割り当てることが可能になり、業務効率化や生産性向上を図ることができます。また、単純作業にミスは付き物ですが、RPAが単純作業を代行することで「ミスをしてはならない」という従業員の心理的プレッシャーを軽減する効果があります。
RPAに必要な性能とは?
では、DX推進のために導入するRPAにはどのような性能が求められるのでしょうか。
それはプログラミングや専門知識、そしてIT技術者を必要としない「現場で作って使える」RPAです。
レガシーシステムように他者の手でRPAのルールが策定されて、複雑化・ブラックボックス化してしまうことは避けなければなりません。そこで、現場レベルでも簡単にルールの作成・修正が可能なRPAがDX推進には必要不可欠です。また、あらゆる業務を自動化するためにはあらゆるアプリケーションはもちろんのこと、場合によっては基幹システムに対応できる性能のRPAであることも重要です。
RPAの浸透に必要な人材育成
DX推進のためにはまず、RPAという低単価で導入できるツールを足がかりに社内の理解を深めていく必要があります。
そのためにRPAの導入を目的にするのではなく、RPAを使いこなすための「プロセス思考」を身につけた社員の育成が不可欠です。ロボパットDX(https://fce-pat.co.jp/)は安心のサポート体制があることから、RPA人材育成にも向いているツールです。
まとめ
「RPAを導入してDXを推進するにはどのようなステップを踏めばよいか分からない」という方に向けて、『「⽇本型DX」に向けて組織的にRPAを活⽤していくための3ステップ』という資料にポイントをまとめました。RPAに少しでも興味を持たれた方は、ぜひこちらもチェックしてみてください。
https://fce-pat.co.jp/download/point04.php