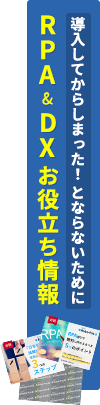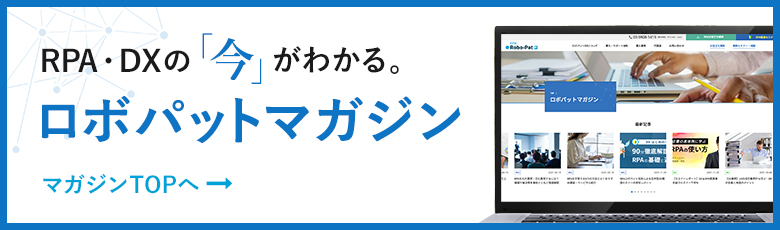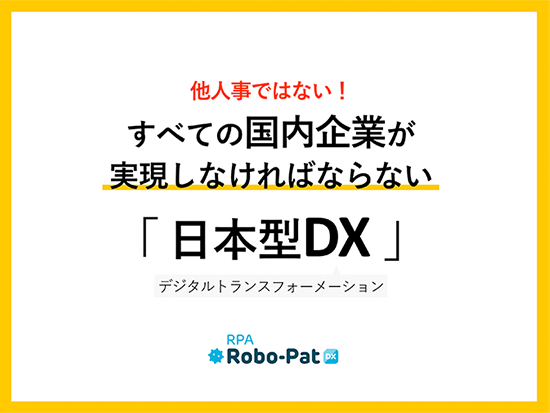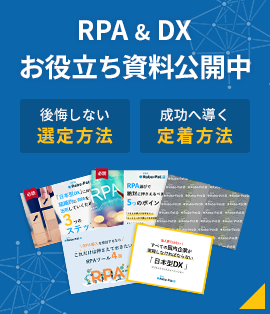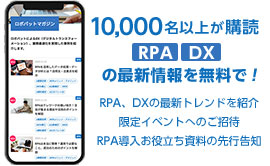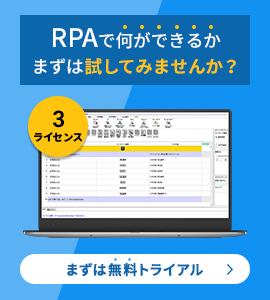DXとは?
「DX(Digital Transformation)」とは、時代の変化に合わせてIT技術を活用し、競争力を持った新たな製品やビジネスモデルを創出することです。経済産業省は「DXレポート」で、DXを以下のように定義しています。
企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること
引用:DXレポート|経済産業省
たとえば、DVD宅配サービスから動画配信サービスに転換した「Netflix」や、空いている部屋や家を貸し出すマッチングサービス「Airbnb」などが、代表的なDX事例です。
中小企業だからこそDXが必要な理由
既存ビジネスからIT技術を活用し、新しい商品・サービス・ビジネスモデルの創出を目指す行うDX。これだけを見ると、中小企業には縁が遠いように思われるかもしれません。
しかし以下5つの観点から、実は中小企業だからこそDXの重要性は高く、さまざまなメリットが得られます。
- 生産性向上が急務である
- 「DX投資促進税制」による節税ができる
- 低コストで導入できるDXツールが増えている
- 既存システムの老朽化リスクを防げる
- 2025年の崖への対策ができる
生産性向上が急務である
中小企業にもDXが必要な大きな理由は、DXによって生産性の向上が期待できることです。大手企業に比べ人手不足がより深刻化している中小企業にとって、少ない人員で従来と同等以上の利益を上げることは重要な課題であり、それを可能にする施策のひとつがDXです。
具体的には、RPAなどの業務自動化ツールや、マーケティングオートメーションツールなどの導入があげられます。これらのツールで業務効率化が進めば、従業員はより生産性の高い業務やビジネスモデルの創出に集中でき、生産性向上の可能性が高まるでしょう。
中小企業にとって、中長期的なリソースの確保は容易ではありません。しかし、業務効率化を進めない限り、企業の業績を上げていくことは困難です。DX導入は短期的にはコストがかかりますが、中長期的な観点では多大なリターンが期待できます。
「DX投資促進税制」による節税ができる
実は、DX導入のための投資は節税にもつながります。政府は2022年度より、DXの実現に必要なデジタル技術への投資に対し、税額控除や特別償却などの優遇措置を始めています。コスト面でDX導入に踏み切れない中小企業は少なくありませんが、節税につながるのであれば検討しやすくなるのではないでしょうか。
低コストで導入できるDXツールが増えている
中小企業におけるDX推進は、コスト面で課題があるケースが多いですが、近年では低コストで導入できるDXツール・ITシステムが増えています。とくに、クラウド上で利用できるRPAツールなどは、わずかなコストで導入できるものが多いです。
また、そもそもDXはいきなり全部門で始めるのではなく、一部門を対象にスモールスタートで導入するのが基本です。コストを抑えてDXに取り組み、効果が出始めてから全社に浸透させることができるので、中小企業でもDXは気軽に取り組めます。
既存システムの老朽化リスクを防げる
前述したDXレポートでは、約8割の企業で既存システムの「老朽化」が進んでいるとしています。ITシステムの老朽化には、以下3つの大きなリスクがあります。
古いシステムを使い続けていると、カスタマイズや維持管理費用が高額化するリスクがあります。さらに、カスタマイズが繰り返されたシステムは複雑化し、一部の人しか扱えない「属人化」したものになりがちです。その担当者が異動・退職などで居なくなると、システム自体が使えなくなってしまうかもしれません。
こうした理由から、老朽化したシステムはIT予算の多くを「保守」に費やすことにつながり、新たなサービスやビジネスモデルの創出のためのリソースが不足します。顧客ニーズや市場の変化への臨機応変な対応も難しくなるので、競合他社に対する優位性も失ってしまうかもしれません。
このように、既存システムをいつまでも使い続けていると、企業の将来性に重大な懸念が生じかねません。企業リソースが限られている中小企業だからこそ、DX推進の必要性が高まっているといえます。
2025年の崖への対策ができる
経済産業省が「DXレポート」を公開し、各企業にDXを促した最大の理由が「2025年の崖」です。
「2025年の崖」とは、「基幹システムのSAP・ERPのサポート終了」「IT人材不足の拡大」などの問題により、2025年以降に最大12兆円の経済損失が毎年生じるという予測す。
中小企業がDXを導入することで得られるメリット
中小企業がDXを導入することで得られるメリットについて、以下5つの観点からさらに掘り下げていきましょう。
- 業務効率化と生産性向上が図れる
- テレワーク・ペーパーレス・法改正に対応できる
- 経営判断に必要なデータを蓄積できる
- 人材確保と育成が行いやすくなる
- 高付加価値のビジネスモデルを創出できる
業務効率化と生産性向上が図れる
DXにより、業務効率化と生産性向上が図れます。たとえば、RPAツールなどを導入して定型業務を自動化すると、従業員の負担を軽減できるうえに業務の精度・品質が上がります。人的リソースをよりクリエイティブな分野に活用できるので、全社的な業務効率化と生産性向上が可能です。
テレワーク・ペーパーレス・法改正に対応できる
「改正電帳法」「インボイス制度」「働き方改革」など、企業はさまざまな法改正に対応する必要があります。DXを推進するにあたり、業務プロセス自体の変革も欠かせません。そのため、これまで後回しにしてきたことも、DX推進の際にまとめて実現できます。また、デジタルツールには法改正対応の機能が搭載されているものが多いため、導入するだけで将来的な工数とコストも省けます。
経営判断に必要なデータを蓄積できる
激化する市場競争を企業が生き残るためには、顧客ニーズや市場動向に対応できる迅速な経営判断が欠かせません。従来の手作業によるデータ収集や分析は、時間がかかるうえに精度の限界もあります。そのため、競合他社に先を越されて、市場における優位性を維持できなくなるケースは珍しくありません。
DXの推進でデジタルツールを導入すれば、さまざまなデータの収集と分析が自動的に行えるようになるため、これまで見えていなかった要素もわかります。顧客ニーズや市場動向を多角的に把握し、迅速かつ的確な経営判断ができるようになるでしょう。
人材確保と育成が行いやすくなる
DX推進は業務プロセスの変革をもたらすので、その過程で「働き方」自体も変わります。業務効率化により労働時間を短縮し、従業員が働きやすい環境を実現できれば、優秀な人材を確保しやすくなります。また、デジタルツールによるデータ収集・分析により、社内ノウハウの蓄積と共有も容易になるので、人材育成の最適化も可能です。従業員にとって魅力的な企業になれば、たとえ人手不足の時代であっても、必要十分な人材を確保・育成できるでしょう。
高付加価値のビジネスモデルを創出できる
DXの究極的な目的は、新たなビジネスモデルを創出し、市場で優位なポジションを築くことです。中小企業には縁の遠い話に思われるかもしれませんが、デジタル技術を駆使すれば事業拡大のチャンスはいたるところで得られます。たとえば、これまで実店舗を主体に展開していた製品を、Eコマース(電子商取引)でも提供すれば、新たな販売機会が得られます。このように、デジタル技術の活用による恩恵は、中小企業こそ大きいのです。
中小企業のDXへの取り組み状況
DXを実践しないことで、さまざまなリスクが生まれる可能性があるものの、多くの企業でが進んでいません。経済産業省が2020年に発表した「DXレポート2」によると、調査を行った企業の9割以上がDXにまったく未着手、もしくは、散発的な実施に留まっています。
また、2021年9月に一般社団法人日本能率協会が発表した「日本企業の経営課題2021」によると、大企業の65.6%がDXの取り組みを始めているのに対し、中小企業はわずか27.7%でした。さらに、DXに取り組む予定はないと回答した割合は、大企業は0%ですが中小企業は10.9%に及びます。
これらの結果を踏まえると、中小企業はDXへの取り組みがとくに進んでいないことが分かります。
参照:
『日本企業の経営課題2021』 調査結果速報 【第3弾】|一般社団法人日本能率協会
中小企業のDX推進における課題点とは
中小企業でDXへの取り組みが進んでいない理由として、以下3つの背景が考えられます。
- IT人材の不足
- DXの重要性や必要性を認識できていない
- IT予算の確保が難しい
IT人材の不足
経済産業省の「DXレポート」によると、2025年に約43万人のIT人材が不足すると考えられています。自社にIT人材を抱える中小企業は少ないため、IT化はどうしてもSIer(システムインテグレータ)に頼らざるを得ません。
つまり、SIerやITベンダー以外の中小企業では、社内でIT人材の育成を促進する体制が整っておらず、AI・IoTなど新技術の導入が難しいということです。これは、中小企業にとって非常に大きな課題のひとつだといえます。
DXの重要性や必要性を認識できていない
中小企業の約1割が「DX行う予定がない」と回答したことからも分かるように、DXの重要性を認識できていない中小企業は少なくありません。
これには、主に2つの理由が考えられるでしょう。現時点で市場で優位性を確保しているのでDXは必要ないと考えるケースと、既存システムの刷新がDXだと認識しているケースです。そのため、現時点で既存システムが問題なく動いていれば、「DXは必要ない」と判断してしまうのです。
IT予算の確保が難しい
DXの実現には、システムの刷新・新たな商品の開発・ビジネスモデルの創出など、多くのIT投資が必要です。しかし、不確実な結果に対して大きな予算を割けないケースも多く、DXを推進できない要因となっています。
中小企業がDX推進を成功させる5つのポイント
中小企業がさまざまな課題を解消しつつ、DX推進を成功させるためには、以下5つのポイントを意識することが重要です。
- DX推進の戦略やゴールを明確にする
- DX推進のための組織を作る
- 経営層がリーダーシップを取り指揮する
- 全社で情報共有体制を作る
- 政府の補助金・助成金を利用する
DX推進の戦略やゴールを明確にする
なぜDXに取り組むのか、何を達成したいのか、戦略・ゴール・ビジョンを明確にしましょう。
たとえば、既存システムを刷新すれば部分的な業務効率化は可能です。しかし、業務効率化をさせたうえで何をしたいかというビジョンがなければ、DXは実現できません。なぜなら、DXの意義は業務効率化や生産性向上の先にあるからです。
まずは、経営陣を筆頭に全社的にDXの重要性を理解し、これからの自社が進むべき道をしっかりと検討することが重要です。そのうえで、先へ進むための具体的な戦略を策定しましょう。
DX推進のための組織を作る
DXは少数の人材で推進できるものではないので、専門の組織体制を構築する必要があります。DXは企業の将来を決める重要な取り組みなので、推進組織のメンバーはできれば既存業務との兼任ではなく、DX専任の人材を任命するのが理想的です。
その際に、現場の担当者もしくは現場での経験が豊富な人材を起用することが重要です。DXのシステムを活用するのは、現場で実務を担当する従業員がメインであることが多いので、現場を無視したDX推進は成立しません。ITスキルが高い人材はもちろん、経営陣から現場まで、バランスの良いメンバー構成を意識しましょう。
経営層がリーダーシップを取り指揮する
前項でも触れたように、DX推進は企業の将来を見据えて行うものなので、経営層がリーダーシップを取って指揮することが欠かせません。経営層の理解なきDXは、失敗してしまう可能性が高いので注意が必要です。
また、経営層が先頭に立つことで、全従業員に対しDXに本気で取り組んでいる姿勢を見せることができ、社内の意識改革も進みやすくなります。実際に細かな戦略を実行するのは現場の従業員ですが、それを予算や人員の面でフォローできる体制を整備するためにも、経営層が率先して進めることが重要です。
全社で情報共有体制を作る
DXの推進は、全社的に同じ方向に向かって進めていく必要があります。そこで重要となるのが、綿密な情報共有体制の構築です。リーダーシップを取る経営層と、実務を担当する現場の従業員との間で、取り組む意識と方向性を統一できるような工夫が欠かせません。
ただし、定例会議や個別ミーティングなどを増やして情報共有に時間をかけ過ぎると、逆に効率が悪くなる可能性もあります。グループウェアや社内チャットの活用、スタンディングミーティングの導入など、気軽に話し合える機会を設けることも重要です。
政府の補助金・助成金を利用する
DXの導入にはコストがかかります。そこで、前述した税制上の優遇措置と合わせて、政府の「補助金」「助成金」もぜひ活用してみましょう。なかでも「IT導入補助金」は、DX推進のコスト削減につながるので、ぜひとも利用したいところです。ただし、補助金や助成金には一定の条件が設けられているので、事前に詳細を確認しておきましょう。
中小企業のDX推進成功事例
実際にDX推進を成功させた中小企業の事例を3つ紹介します。
陣屋の事例
老舗旅館「陣屋」は2009年に10億円もの負債を抱え、一時は倒産寸前でした。同旅館が実施したDX施策は、内製システムの導入による「全社員での情報共有」「情報の透明化」です。
外部からシステムを導入する予算がなかったため、エンジニア経験のあった社員を中心に、基幹システムとなる「陣屋コネクト」を開発しました。これを活用し、アルバイトも含めた全従業員で顧客情報を共有し、迅速かつ適切なサービス提供を実現しました。
さらに、戦略や財務状況なども同システム上で公開し、数字を共有するだけの会議を廃止し、さらなる業務効率化が進んでいます。これらの取り組みで、売上黒字化に加えてシステムの販売という新規事業も創出でき、収益大幅にアップしています。
株式会社ZEN PLACEの事例
「株式会社ZEN PLACE」は、全国100店舗以上のヨガ・ピラティス専門スタジオを展開しています。同社では、各地に点在するスタジオとの連絡に膨大な時間と手間がかかることや、回答内容の不統一による顧客サービスの品質低下などの課題を抱えていました。
そこで同社は、問い合わせ対応を自動化する「チャットボット」を導入しました。問い合わせ内容をいくつかのカテゴリに分け、それぞれの回答をチャットボットで自動化します。さらに、これまで曖昧だった問い合わせ対応のルールを統一したことで、担当者の負荷軽減に加えて顧客サービスの品質向上にも成功しました。
さらに、チャットボット導入で効率化が進んだことで余力が生まれ、2022年1月から著名ピラティス講師のオンラインLIVEレッスンという、新規事業もスタートさせています。
出典:店舗スタッフからの問い合わせ対応にかかっていた時間を約93%削減!
日東電機製作所の事例
「日東電機製作所」は、電力・産業・コンピュータ・医療用など、さまざまな分野での開発業務を展開しています。同社では、これまで設計部門のルーティンワークに人員を割いており、その手間とコストに課題を抱えていました。
そこで同社は、データの印刷と押印の作業を自動化するためにRPAを導入しました。この作業に従事していた従業員をより生産性の高い業務に配置し、業務効率化と生産性向上を実現しました。
出典:中小企業のDXは「低予算」から!メリット・成功ポイントを解説
まとめ
昨今は新型コロナウィルスの影響もあり、テレワークやペーパーレス化など、働き方が大きく変革しています。中小企業だからこそ、DXによる業務効率化と生産性向上のメリットが得やすいので、できるだけ早くDXに取り組むことを検討してみましょう。
中小企業のDX第一歩としておすすめしたいのが、日東電機製作所の事例でもご紹介した「RPA」です。RPAはルーティンワークを自動化できるので、さまざまな業種・部門でDXの効果が得られます。
弊社では、特別なITスキルを必要としないRPAツール「ロボパットDX」を提供しています。現場の担当者が自身の作業を簡単に自動化できるので、中小企業での導入実績も豊富です。RPAに興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご相談ください。