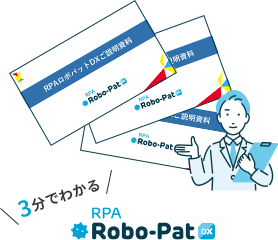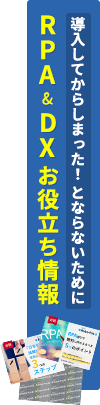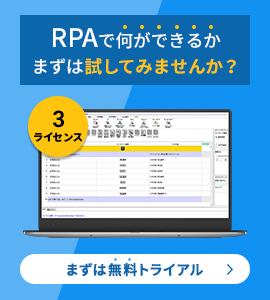経済産業省の「DX推進ガイドライン」
「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」(以下、「DX推進ガイドライン」)とは、DXの実現やその基盤となるITシステムの構築をおこなっていくうえで経営者が押さえるべき事項を明確にすること、取締役会や株主がDXの取り組みをチェックするうえで活用することを目的として、経済産業省が2018年12月に策定したものです。
「DX推進ガイドライン」における10個のポイント
「DX推進ガイドライン」は大きく分けて、「(1)DX 推進のための経営のあり方、仕組み」と、「(2)DX を実現するうえで基盤となる IT システムの構築」から構成されています。
「(1)DX 推進のための経営のあり方、仕組み」では、「経営戦略・ビジョンの提示」「経営トップのコミットメント」「DX推進のための体制整備」「投資等の意思決定のあり方」「DXにより実現すべきもの:スピーディな変化への対応力」という5つの項目が挙げられています。
また、「(2)DX を実現するうえで基盤となる IT システムの構築」は、「(2)- 1 体制・仕組み」として「全社的なITシステムの構築のための体制」「全社的なITシステムの構築に向けたガバナンス」「事業部門のオーナーシップと要件定義能力」という3項目が挙げられ、「(2)- 2 実行プロセス」としても「IT資産の分析・評価」「IT資産の仕訳とプランニング」「刷新後のITシステム:変化への追従力」という3項目の、合わせて6項目が挙げられています。
この計11項目の内容に対して、10個のポイントに整理し直して解説していきます。
経営者による明確なビジョンの提示
項目1の「経営戦略・ビジョンの提示」では、デジタルディスラプションについて言及しています。デジタルディスラプションとは、近年、世界で発生している「すでにある産業を根底から揺るがして崩壊させてしまうような、デジタルテクノロジーによる革新的なイノベーション」のことを意味しています。
分かりやすい例として、小売業を根底から大きく変えていったAmazon、レンタルビデオ/DVDの世界を映像ストリーミング配信事業で変革したNetflixなどが挙げられます。
経営者は自らの業界にデジタルディスラプションが起こることを想定しながら、自社がおこなっている事業分野において、「どのような新たな価値(新ビジネスの創出、即時性、コスト削減など)を生み出すことを目指しているのか」「そのためにどのようなビジネスモデルを構築すべきなのか」というような経営戦略やビジョンを、具体的に自社内に提示する必要があります。
変革に対する経営トップの強い意志
DXで成功するには、ビジネスや仕事の仕方、組織・人事の仕組み、企業文化・風土そのものの変革が不可欠です。そのため、DXの推進に経営トップがコミットメントし、変革に対する強い意志を持って取り組んでいく必要があります。
もし、自社のDXの推進に対して社内で大きい抵抗があったときは、経営トップがリーダーシップを発揮しながら、DX推進への意思決定をしなければいけません。
経営層の投資に対する意識・判断力
企業がDXを推進するためには、一時的に変革に対する投資が必要となってきます。DX推進のために、そのときにコストだけを見るのではなく、ビジネスに与えるプラスのインパクトを勘案して判断する必要があります。
その際に、経営層の意識・判断力が問われます。投資をせずDXが推進されないことで、デジタル化するマーケットから排除されるリスクを勘案しなければいけません。また、定量的なリターンやその確度を経営層が求めすぎているとDXに対するチャレンジを阻害し、成長要因をそがれることになります。
迅速な施策実行が実現できる社内体制の構築
DXの推進で引き起こされる自社のビジネスモデルの変革によって、経営方針の転換やグローバル展開などというような施策実行が迅速に実現できるよう、社内体制を構築する必要があります。
人材の獲得・育成
DX導入を成功するためには、DXの推進に必要なIT人材の獲得・育成が必要です。そこで、DX推進部門においてはデジタル技術やデータ活用に精通したIT人材を獲得・育成しましょう。
また各事業部門でも、業務内容に精通しているだけでなくデジタルで何ができるかを理解している人材を獲得・育成することで、DXへの取り組みが進むようになります。
しかし、日本ではさまざまな業界・業種でIT人材の不足が起きています。そこで、IT人材の社外からの獲得や社外との連携も視野に入れましょう。さらに、エンジニアに依存しない「日本型DX」を目指し、クラウドサービスをはじめとする汎用型システムやノーコード/ローコードで開発したITシステムを活用するというような取り組みも大切です。
部門間におけるシステムの統一や連携
企業がDXを推進するために社内のITシステムの統一化を図っていきますが、その際、新たに導入するITシステムと既存のITシステムとの円滑な連携環境を確保する必要があります。
全社的なITシステムの構築にあたっては、ITベンダー企業に丸投げせず、ユーザーである企業自らがシステム連携基盤の企画・要件定義を行いましょう。
現状の把握
企業がDXを推進していく際に、ご自身の会社のITシステムの現状を把握しておくことが必要です。現状のITシステムの状況を「複雑化しているのか」「ブラックボックス化しているのか」などを理解して初めて、ITシステムの刷新ができるようになります。
自身の現状を把握していないまま、ITシステムを刷新することは結果としてITベンダー企業に丸投げとなってしまいますし、「システムは新しくなったけれどもブラックボックス化は変わらない」というような事態に陥ることになりかねません。
全体最適化のための視点
ITシステムが事業部門ごとに個別最適化してしまうと、ITシステムが複雑化・ブラックボックス化してしまいます。そうならないよう、ITシステムの全体最適化が必要です。
ITシステムが個別最適化をしていると、二重入力などの人材の無駄が発生するほか、保守メンテナンスコストも余計に必要となり、DXに対して多くのリソースを割くことが難しくなります。そこで、システム開発者が全体最適化のための視点を持ちながら、一貫性を持ったシステムを設計し構築していく必要があります。
全体最適化の視点を持った人材は、デジタルのスキルだけ持っていても、ビジネスのスキルだけを持っていても務まりません。デジタルとビジネスのスキルを併せ持ったIT人材が求められます。
各部門の積極的な参加
要件の詳細はベンダー企業と組んで一緒に策定していくのでもよいのですが、要件定義はベンダー企業に丸投げをせずユーザーである企業が確定することで、DXを推進できるようになります。
新しい技術への対応力
企業がDXを推進していくためには、経営層がリーダーシップを持つことが必要です。とはいえ、代表取締役やCEO(Chief Executive Officer/最高経営責任者)が「ITリテラシーが高い」とは限りません。
その場合、経営の視点でデジタル変革を推進する役割を持つCDO(Chief Data Officer/最高データ責任者)を経営層に迎え入れ、新しい技術への対応力を高めるようにしましょう。
日本企業にとって「DX推進ガイドライン」準拠は難しい?
経済産業省が発表した「DX 推進ガイドライン」は、DXを推進するための基本的なことだけが書かれているので、日本企業でも簡単に準拠はできるかと思います。
しかし日本企業は、以下のような方法でDXを推進しようとする企業も多く存在します。DXは「IT化」ではありません。昨今話題に上がりました「働き方改革」にも密接に関係します。そこには日本企業特有の課題が存在します。
そのため、以下のような方法でデジタル化をしてもDXの導入・推進は成功しないのです。
システム導入だけでDXを推進しようとしがち
「DXとは、デジタル技術やデータを活用することで、業務方法やビジネスモデルを変革すること」だと聞いて、最新システムを一気に導入してIT化を進めたとしてもDXが推進されたわけではありません。
IT化とは業務効率化などというような「目的」に対して、デジタル化や情報化を進めるものでした。それに対しDXとは、DXの推進を「手段」として企業の変革を成果として進めていくものです。
DXの推進に成功している企業は、既存の個別領域をデジタルに適用させていくことで組織を変革し、新しいビジネスモデルへと転換していっています。
日々、新たなシステムを導入していくことで自社をアップグレードし続けてはいますが、新たなITシステムを無理やり一気に導入せず、旧システムも見直しつつ徐々に移行させている企業がDXのことを真に理解しているといえるでしょう。
システム部門や外部ITベンダーに丸投げしがち
企業がDXを導入する際、DXを推進していく役割はシステム部門や新設したDX推進部門などになります。しかしDXは、企業を「イノベーションする」「デジタル化する」「変革する」というような異なった目的が共存しています。
このような目的の達成を、システム部門やDX推進部門に丸投げするのは無理があります。システム部門やDX推進部門はDX推進を指揮するところとして、経営層や現場部門を含めた全社的な取り組みにしていく必要があります。
同時に、外部のITベンダーにDX推進を丸投げすることもよくありません。ITベンダーは最新のITシステムを提案し導入することは得意ですが、既存のビジネスモデルやビジネスプロセスを変革し、新たな価値を創出することはできません。
「最新ITシステムの導入にコストだけをかけてDXは成功しない」という事態を招きたくなければ、外部ITベンダーへの丸投げは避けるべきです。
「現場社員自ら実行できること」が重要
各事業部門がオーナーシップを持って、DXで実現したい事業企画や業務企画を現場社員自らで明確にし、実行できることが重要です。
DXの推進を経営層やDX推進部門やシステム部門だけに任せるのではなく、現場自らも積極的に関わってDXを推進していくことで、全社一丸となったDXの成功を実現することができます。
まとめ
今回の記事で、経済産業省が発表した「DX推進ガイドライン」の概要はご理解いただけたかと思います。
企業がDXを推進するために「DX推進ガイドライン」で書かれていることが参考になりますが、日本企業の場合、「日本型DX」という考え方も考慮してDXを推進していく必要があります。
最後に、「日本型DX」の実現に役立つ非エンジニア型の国産RPAツール「ロボパットDX」についてご紹介します。
ロボパットDXは「事業部門が自分で自動化できるRPA」というコンセプトで生まれました。企業に必要とされる機能、「現場」の業務フローを追求しながら改善を重ねてきた、日本企業のDX導入を推進するのに最適なRPAツールといえます。
各種研修、トライアルを通じて、ロボパットDXの運用方法を担当者がしっかりと習得できるよう、ロボパットDXはサポート体制が非常に充実しています。
中小企業でのDX推進事例も数多くありますので、本記事で興味が湧いた方は、ぜひロボパットDXの詳細を確認してみてください。
また、ロボパットDXは導入実績1,000社以上のサポートから見えてきたRPA定着のノウハウをすべて公開した資料も提供しています。
ぜひチェックしてみてください。
https://fce-pat.co.jp/download/