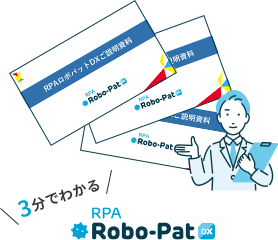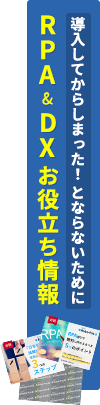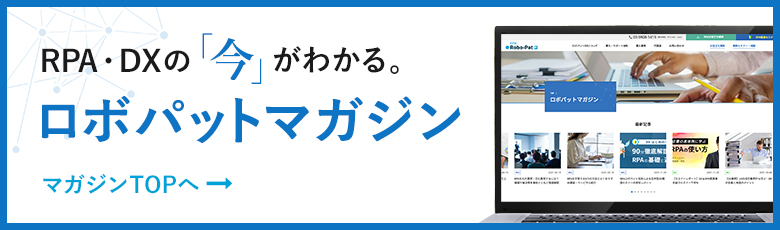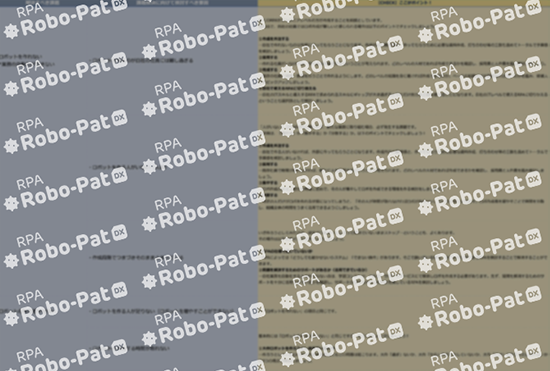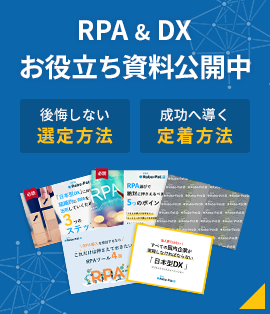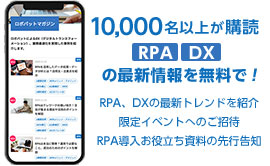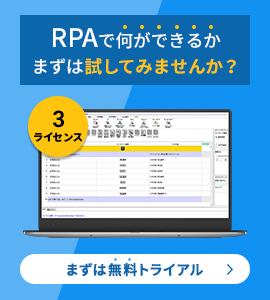RPAとは?
RPAとは「Robotic Process Automation」の略で、これまで人間が行ってきたパソコン上の定型業務を、ソフトウェアのロボットに代行させて自動化する仕組みのことです。
よく似た技術に「マクロ」がありますが、マクロが特定のアプリケーション(Excelなど)内での作業を自動化するのに対し、RPAツールはアプリケーションを横断した、より広範囲なPC操作(例:Webブラウザから情報を収集し、Excelに転記して、基幹システムに入力する、など)を自動化できるのが大きな違いです。
データの入力や転記、収集・統合、クリックやキーボード操作など、ルールが決まっている単純作業を24時間365日、人間の代わりに対応できます。
少子高齢化による労働人口の減少や、働き方改革への対応が急務となる現代において、RPAは多くの企業の救世主となりうる可能性を秘めているのです。
RPAは使えない!?導入に失敗する3つのパターン
鳴り物入りでRPAを導入したものの、現場から「使えない」という声が上がるのには、明確な理由があります。 ここでは、代表的な失敗のパターンを3つご紹介します。自社に当てはまるものがないか、チェックしてみてください。
【パターン1】価格重視でRPAを選んだ結果、費用対効果が期待外れに
RPAツールの導入でよくある失敗が、価格の安さだけでツールを選定してしまい、自社に最適なRPAを選定できなかったケースです。
例えば「自社のアプリが動かない」「運用してみると難しくて使えなかった」「必要な機能がなかった」などの理由が、こちらに該当します。
特に海外製の安価なツールは、プログラミングの知識が必要など専門知識を持つエンジニアが使うことを前提に作られていることが多く、IT初心者には設定が難しい場合があります。
さらに、ベンダーに頼ろうにもサポート費用がかなり高額になるなど、導入後に後悔するケースもあります。
RPAを選定するときには、まずどの部門で使うのかという点を明確にしておかなくてはいけません。
情報システム部門のスタッフなど、ITリテラシーが高い方が扱う場合は、どんなRPAでも使いこなせるかもしれません。しかし、現場のスタッフが使う場合には、誰にでも使いやすい簡単なRPAを選択する必要があります。
結局、専門のエンジニアでなければ扱えないため、簡単なロボット作成さえも外注することになり、ライセンス費用は安いものの、最終的な費用対効果が見合わない「期待外れ」な結果に終わってしまいます。
ベンダーによっては無料トライアルを提供しているところもあるので、導入前に実際に現場で使ってみることも大切です。
【パターン2】現場でRPAが浸透せず属人化する
「鳴り物入りで導入してみたが、現場におけるRPA活用の優先順位が高まらなかった」というケースも、よくある失敗例のひとつです
情報システム部門が主導してRPA導入を進めたものの、現場がそのツールを「自分たちのもの」として捉えられず、浸透が進まないケースです。現場スタッフが使いこなせないRPAを導入した企業や、RPAの導入目的や効果を事前にスタッフへ説明しなかった企業によくみられます。
導入当初はいくつかの業務を自動化できたとしても、業務フローの変更やエラー発生時に、現場で対応できる人がいません。
結果、RPAの運用・管理が特定の担当者に集中して「属人化」してしまい、その担当者が異動や退職をすると、誰もロボットをメンテナンスできず、RPAの活用が止まってしまいます。 これでは、何のために導入したのか分からず、まさに「無意味」な投資となってしまいます。
現場にRPAを浸透させるためには、導入検討段階から現場のスタッフを巻き込むことが重要なポイントです。
そのためにはRPA導入の意義を、作業者だけでなく現場のスタッフ全員に具体的に理解してもらう活動の実施が欠かせません。「RPAを実際に操作する」「勉強する時間も業務としてしっかり取る」など、RPA導入を組織として応援する姿勢も大切です。
また、経営層が「RPA導入による業務効率化は、企業の重要命題である」ことを名言することも、RPAを現場へ浸透させるためには不可欠でしょう。
【パターン3】業務の自動化に失敗…
3つ目のよくある失敗例は、RPAによる業務の自動化がうまくいかないケースです。例えば「選んだ業務がうまく自動化できなかった」という事態がこちらに該当します。
RPAは魔法の杖ではありません。自動化する業務の選定を間違えると、導入は失敗に終わります。
要因としては、
- 現場の業務知識がない方が、工数削減の視点だけで対象業務を選んでしまう
- 業務整理をせずにいきなり導入してしまう
- 業務の全行程を自動化しようとして自動化の難易度が上がってしまい、途中で頓挫した
などが考えられるでしょう。
例えば、頻繁にルールや手順が変わる業務や、人間の柔軟な判断が必要な業務を無理に自動化しようとすると、エラーが多発し、かえって人の手による修正作業が増えてしまいます。
また、業務の結果をまとめる際のフォーマットにばらつきがあることや、業務フローやルールが統一できず自動化に難航した場合にも、RPAによる作業の自動化に失敗する可能性が高くなります。
「自動化できるはず」と見切り発車で進めた結果、RPAが頻繁に止まり、その原因調査と修正に追われる…という本末転倒な事態に陥るのです。
したがって、RPAを導入する際には、対策検討段階から現場スタッフと一緒に考え、現場が楽になる業務から優先的に自動化することが重要です。全行程の自動化にはこだわらず、工程ごとに自動化したり、業務フローをRPAに合わせて柔軟に見直したりしましょう。
RPAで自動化すべきものとすべきではないもの
RPAの導入で失敗しないためには、RPAに「できること」と「できないこと」を正しく理解し、自動化に適した業務を見極めることが重要です。
RPAができること・できないこと
【RPAができること(得意な業務)の例】
RPAによる自動化に適した作業は、手順やルールが毎回同じ作業です。RPAはルール化されているものを素早く繰り返し処理することが得意なため、Excelなどのデータ入力や定型データの情報読み取りといった作業の自動化に適しているといえます。
- ルールが明確な定型業務
- 繰り返し行う単純作業
- 複数のアプリケーションをまたいだデータの転記・入力(例:請求書PDFから会計ソフトへの入力)
- 定期的なレポート作成
- Webサイトからの情報収集とリスト化
【RPAができないこと(苦手な業務)の例】
- 人間の判断や意思決定が必要な業務(例:クレーム対応、クリエイティブな企画立案)
- 頻繁に手順や画面デザインが変わる業務
- 紙媒体の情報を読み取ること(※AI-OCRとの連携で可能になる場合もあります)
- 物理的な作業
よくAIと一緒に語られることの多いRPAですが、AIと違って判断が伴う作業は苦手です。
このような作業はRPAで無理やり自動化しようとせず、アウトソーシングや専用システム構築などの代替策を考えることも必要です。したがって、RPAを導入する際には、人がおこなう作業とRPAで自動化する作業を棲み分けておく必要があります。
RPAで自動化すべきではない業務とは?
業務の中には、RPAで自動化することは可能ですが、敢えて自動化しないほうがよいものもあります。
そもそも不要な業務
長年の慣習で続けているだけで、実は誰も見ていない報告書や、形骸化したチェック作業など、そもそも業務自体をなくせる可能性があります。
RPAの導入時には業務の棚卸を実施して、業務の優先順位や自動化する業務の選別を実施します。その際、意味がない業務や非効率な業務、慣例的に実施されている業務、同じような作業の重複などがみられることが多くあります。
RPAで業務を自動化して生産性を向上させるためには、業務フローを根本的に見直す必要があるため、不要な業務をカットする決断も余儀なくされるでしょう。業務フローを最適化したうえで、RPAによる自動化をおこなうことで、高い生産性向上効果が期待できるのです。
自動化を検討する前に、まずはその業務が本当に必要かを見直しましょう。
RPA導入の失敗原因を乗り越え、成功に導くポイント
ここまで紹介した失敗例や原因を踏まえ、RPAの導入と活用を成功させるための具体的なポイントを解説します。ツールの選び方から、導入後の進め方まで、ぜひ参考にしてください。
現場主導で十分に使いこなせるRPAを選ぶ
RPA導入成功の最大のカギは、ITの専門家であるエンジニアでなくても、現場の業務担当者自身が「使いこなせる」ツールを選ぶことです。
現場主導で使いこなせるRPAを選択するポイントは、以下の通りです。
- プログラム言語を知らなくても、ロボットの作成・修正ができること
- 煩雑な操作が必要なく、普段の手順通りにRPAで作業の自動化ができること
- 画像認識などを利用し、誰にでも利用できる直感的なUI・UXであること
- 導入前に無料トライアル期間があること
プログラミングの知識がなくても、日々のクリック操作などを録画するだけで直感的にロボットを作成できるツールなら、IT初心者でも無理なく扱えます。
自社製品である「ロボパットDX」は、まさに現場の担当者が使いこなすことを徹底的に追求して開発されたRPAツールです。
ベンダーのサポート体制とツールの選び方
ツールの機能だけでなく、ベンダーによるサポート体制も重要な選び方の基準です。
導入時のトレーニングはもちろん、どの業務を自動化すべきか相談できたり、エラー発生時にすぐ質問できたりする手厚いサポートがあれば、初心者でも安心して活用を進められます。
無料トライアルなどを活用し、ツールの使いやすさとベンダーのサポート品質を両方見極めることが、失敗しないための賢い選び方です。
現場スタッフも交えてトライアルを活用
無料トライアルの際には、現場のスタッフも交えてRPAのトライアルを進め、サポートを十分に活用して積極的に自社で活用を進めることが大切です。
まず、トライアルを実施する前に、以下のポイントを押さえるようにしましょう。
- RPAの導入目的とトライアルのゴールを明確化する
- 検討段階から現場スタッフを巻き込んで導入を推進する
- RPAの扱いに向いたスタッフを複数名選び、トライアルメンバーにする
RPAに限らず、自分たちの業務に変化が起こるような新しいツールやシステムを導入する際には、少なからず現場スタッフからの反発が予想されます。そのため、RPAによる業務効率化プロジェクトを自分事にしてもらうための工夫が欠かせません。
次に、実際にトライアル開始後も以下のポイントを押さえることで、現場へのRPA導入がスムーズにおこなえるようになるでしょう。
- 基本操作を覚えたら、まずは遊び感覚でロボットを作ってみる
- ・ベンダーのサポートを最大限活用する
- ・RPA導入を後押しする雰囲気をつくり出す
- ・RPAの勉強は業務として扱う
- ・スタッフ同士で進捗を確認する機会を設ける
RPAを活用した業務効率化の実現が、重要なミッションであることをコミットするとともに、そのために必要なサポートを企業側が全力で実施することで、はじめて現場でRPAを導入しようという風土がつくられるのです。
現場が本当に負担を感じている業務から自動化する
RPAを導入すると、自動化したい業務がたくさんリストアップされると思います。そのため、自動化を実施する業務の優先順位をつけて対応しなくてはいけません。
なお、業務の優先順位をつける場合には、以下の3点に留意しましょう。
- 現場で本当に負担となっている業務は何か?
- 一部でも自動化できれば、現場スタッフが楽になる業務は何か?
- 現場スタッフが「面倒……」「手離れできたら嬉しい」と思っている業務は何か?
RPAで作業を自動化する際には、工数削減効果が高い業務を選びがちです。しかし、大きな工数削減効果がなくても、繁忙期や複数の業務が重なる場合には、自動化するだけでスタッフの負担が大きく下がるものもあります。
また、自動化による工数削減効果が高い作業だったとしても、現場のスタッフのコア業務に該当する場合は「ロボットがコア業務をやるなら私は不要なの?」と不安をあおる可能性もあるでしょう。
RPAで自動化する業務の優先順位を決める際には、できるだけスタッフの本音を聞き出す工夫をしたうえで、本当に自動化したい業務を見極めることが重要です。
RPA導入の目的は、現場の負担を軽減し、生産性を上げることです。
情報システム部門がトップダウンで対象業務を決めるのではなく、現場のスタッフにヒアリングを行い、「この作業がなくなれば本当に助かる」という業務から自動化を始めましょう。
現場が効果を実感することで、RPAへの協力体制が生まれ、浸透もスムーズに進みます。
成功事例を参考に、一部分からでも積極的にRPAを活用する
近年では、多くの企業や地方自治体でもRPAの導入事例が公開されています。 例えば、ある自治体では、定型的な申請書類の処理にRPAを導入し、大幅な時間削減に成功した事例があります。
こうした成功事例を参考にしつつ、最初から業務全体を自動化しようとせず、まずは「データの転記だけ」「ファイルの移動だけ」といった業務の一部分からでも積極的にRPAを活用してみましょう。
RPAを導入した企業の中には「すべての業務を自動化しよう!」といった壮大な目標を掲げるケースを散見します。しかし、業務効率化によって生産性を向上させたい場合は、この考え方は危険といえるでしょう。作業の全行程を自動化するのではなく、業務の一部を自動化し、スモールスタートで成功を収めてから全社へ拡大する方法がおすすめです。
小さな成功体験を積み重ねることが、全社的な活用へと繋がります。
【まとめ】RPAの導入に成功するためのポイントを押さえよう
RPAはその特性や導入時のポイントさえ押さえれば、業務効率化につながり企業の生産性向上が実現できる可能性が高まります。現場スタッフだけにRPAのプロジェクトを丸投げするのではなく、可能であれば経営層からも強い意志を示すべきでしょう。
RPAが「使えない」ツールになるか、「最高の相棒」になるかは、製品の選び方と導入の進め方にかかっています。
RPA導入で失敗する原因の多くは、「価格だけで選ぶ」「現場に浸透しない」「業務選定ミス」に集約されます。
これらの失敗を避け、成功を掴むためには、
- IT初心者でも直感的に使えるツールを選ぶこと
- ベンダーの手厚いサポート体制を活用すること
- 現場の負担が大きい業務からスモールスタートすること
この3つのポイントが非常に重要です。
自社内のスタッフだけで完結させようとせず、ベンダーのサポートをフル活用することもポイントです。そのためにも、サポート体制が厚いRPAベンダーをみつけることが重要となります。
RPAツールをお探しの際には、ぜひ「ロボパットDX」についてもチェックしてみてください。
「ロボパットDX」は現場向けに開発されたサポート体制が非常に厚いRPAツールです。現場への浸透をさまざまな形でサポートいたします。
「ロボパットDX」は、プログラミング知識不要の使いやすさと、業務選定から組織づくりまで伴走する手厚いサポートで、多くの企業のRPA活用を成功に導いています。
もちろん無料トライアル期間も準備していますので、興味が湧いた方は以下よりお気軽にご相談ください。