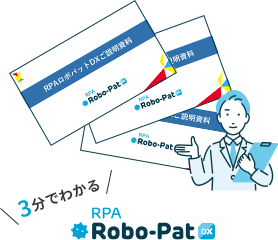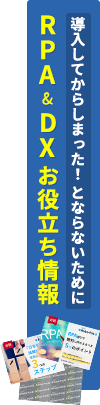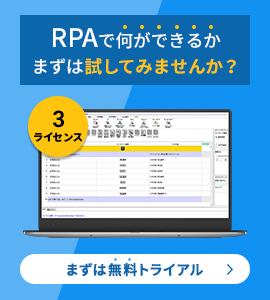RPAの国内外の市場動向
あらゆる業務に効率化が求められる現代、RPAは2016年の「RPA元年」以来、世界中で市場規模を伸ばし続けています。多国籍コンサルティング企業のアクセンチュアの発表によると、全世界でのRPA市場規模は2016年度の2億7千万ドルから、2021年度には21億2千万ドルと4.5倍の規模になることが予想されています。
成長率は、2017年の63%から2021年度には20%と下落する予想ですが、平均成長率は35%と高くなる傾向と予想。これらの数値化から、国際規模でのRPA市場は高い水準で加速を続ける状況であることが分かります。
日本国内におけるRPAの市場は、国際市場と比べても非常に活発的です。2017年~2018年の導入成長率で見てみると成長率は124%となり、国際市場においても北米・西欧に続き世界第3位のシェア率となっています。今後の予測としては、2016~2021年度では8.7倍と世界平均以上に拡大する見込みです。
この高い成長率の背景には、経済産業省が主導している「デジタルトランスフォーメーション(以下DX)」が大きく関わっています。なお、DXとRPAの今後については後ほど詳しく解説します。
また、少子高齢化社会における「生産年齢人口の確保」の目的も、日本国内でRPAの導入が進む理由のひとつです。生産年齢人口の確保は多くの日本企業で急務となっており、少子高齢化問題に直面する国内企業にとって経済成長はおろか、現在の経済状況を維持することすら難しい現状です。そこで、最小限の労働力で同じ品質のアウトプットが可能になるRPAを活用して生産性の向上を図ることで、生産年齢人口の確保の実現を目指しているのです。
一方で、現場至上主義の企業風土が残る日本では、業務の詳細がブラックボックス化する傾向があります。この問題は、国内企業がRPAを導入する際に必要な「プロセスの可視化」を妨げ、導入を遅らせているとされていました。しかし、大手金融機関がRPAの導入・運用に成功したことを期に大企業をはじめ、中小企業までもがRPAの導入に着手するようになりました。日経コンピュータの調査によると、2019年時点で大手・中小企業で稼働しているRPAの自動化時間は約610万時間/年を超え、この数値を労働力に換算すると約4万人月にも及びます。
さらに、国内市場でのRPAの盛り上がりを受けて、各メーカーからリリースされているRPAツールのシェア争いも熾烈を極めています。そのため、RPA市場では価格競争が起こっており、今後はRPAの導入・運用にかかるコストが下がっていくことが予想できます。
RPAの普及に伴い、RPAのコンサルティングサービスなども登場しており、RPA関連市場は軒並み成長傾向なので、今後もRPA市場は活発な動きを見せることでしょう。
RPAに注目が集まる理由とは?
RPAに注目が集まっているのには、先述した少子高齢化による生産年齢人口の確保以外にもいくつかの理由が考えられます。具体的には次のとおりです。
ホワイトカラーの業務効率化
これまで業務の自動化というと、工場や生産現場などいわゆるブルーカラーの業務で工業用ロボットを導入し自動化するものでした。
これに対しRPAでは経理・営業・総務など、ホワイトカラーの社員が日々行なっているルーティンワークを自動化します。その結果、ホワイトカラーの業務効率化が実現。空いた時間をコア業務に向けられるため、生産性向上にも期待が持たれています。
部署間を跨ぐ業務の効率化
ホワイトカラーの業務効率化を実現するツール、システムは今までにも多く存在しました。ただ、そのほとんどは独立したもののため連携がとれず、部署内だけで完結しない業務では、かえって非効率になってしまうケースが少なくありません。
しかし、種類にもよるもののRPAの多くはさまざまなシステム、ツールと連携が可能なため、部署をまたいだ業務であっても問題なくスムーズに行えるようになります。
ノンプログラミングによる自動化
日本の多くの企業では、社内にプログラマーを置かず、システム導入や改修の際にはSlerやベンダー企業へ依頼するのが一般的です。これは普段、開発業務を行わない多くの企業にとって最も効率的ではありますが、いざシステムの刷新・改修といった際には、多額のコストが必要になります。
RPAは業務内容にもよりますが、多くの業務はプログラミングの知識をそれほど必要としません。そのため、導入の敷居が低いこともRPAが注目を集める理由の一つとなっています。
RPAの今後
ご紹介したとおりRPAは成長を続けていますが、今後は違った展開になることが予測されています。リサーチ企業のガートナーが提唱する「ハイプ・サイクル」によれば、新しいサービス・テクノロジーは熱狂的な時期を過ぎすると反動で幻滅する人が多く発生する「幻滅期」を迎えるとされています。この幻滅期はRPAの今後をどのように左右するのでしょうか。
RPAの「幻滅期」が訪れる?
ハイプ・サイクルの幻滅期とは、新しいサービス・テクノロジーなどが市場登場直後の過度な期待値のピークを過ぎた後、熱狂が冷め期待が転じて幻滅に変わる時期のことです。幻滅期を過ぎると改めて市場に浸透する「啓蒙活動期」を迎え、その後は市場で成熟・認知が進む「生産性の安定期」に入ります。
急速に拡大を続けてきたRPAは、2020年現在が幻滅期にある状況です。RPAの幻滅期では各RPAを導入・運用して生じた課題の解決が必要になり、大量に生まれたRPAの淘汰が同時に起こります。そして今後は、幻滅期の淘汰を乗り越えて啓蒙活動期に入るために、さらなるシェア競争の激化が予測されます。
RPAの利用者にとっては、品質やコストなどの面で大きな進歩が見られると同時に、各RPA導入・運用における成功・失敗のモデルケースがある程度揃うタイミングです。そのため、自社に適したRPAを吟味しやすくなるといったメリットがあります。
多様な選択肢が増える
今後はRPAそのものの種類が増加し、多様な選択肢を得られるようになります。
例えば、RPAシステムベンダーのAutomation Anywhere社が「RaaS(RPA as a Service)」の提供を開始しています。Web上でクラウドサーバー内のRPAにアクセス・操作できるもので、オンプレミス型のシステムをサーバーやパソコンにソフトをインストールする必要がありません。これにより、従来型のRPAでは利用前に必要だった環境構築の手間が省けるとともに、インターネットにつながっていれば端末を問わずにRPAを利用できるようになっています。RaaSには「OSの種類を問わない」「オンプレミス型より低コスト」などの利点もあり、これまでRPAの導入をためらっていた会社でも導入への動きを加速させられるでしょう。
また、国産のRPAでも動きがあります。RPAシステムベンダーのRPAホールディングス株式会社が提供するRPA「BizRobo!」がバージョンアップを行い、特にユーザビリティの大幅な強化に力を入れています。従来はRPAプログラムの開発に2台必要だった端末を1台にまとめるアップデートが実施され、業務を自動化したいパソコン上で直接プログラミングをすることが可能になり、開発速度の上昇とコストの低下を実現。その他にも新機能として、ステップ追加と同時に自動で動作確認してくれる機能が実装されるなど、さまざまな取り組みで開発効率が向上しています。
ただ、これらのRPAは、プログラミング言語の知識が必要だったり、Web上の作業に限定した用途だったりと、まだまだ制約が多いことも事実です。
これからの時代選ばれるRPAとは?
RPAによる自動化の進化は3つのクラスに分けられています。それぞれの概要は次のとおりです。
クラス1 RPA
現在、もっとも普及しているタイプのRPAです。主な業務範囲としては、請求書の作成、販売データの入力、競合他社の商品情報収集というような定型業務の自動化です。
クラス2 EPA(Enhanced Process Automation)
自然言語解析や画像解析、音声解析のほか、構造化されていないデータの収集・分析など、RPAにAIの技術を活用し、一部非定型業務の自動化を行います。具体的には、過去の販売データ、市場規模の推移などの要因を加味した売上予測、OCRとの連携による紙文書の読み取り・自動入力などが挙げられます。
クラス3 CA(Cognitive Automation)
自然言語学習、ビッグデータ分析、機械学習などクラス2をさらに高度化したAI技術を搭載したRPAです。自然な言語によるユーザーとの自動対話、季節や天候、地域などを考慮した仕入管理のほか、社会・経済情勢を鑑みたうえでの経営判断などを行います。
クラス2や3のRPAが登場するまでにはまだだいぶ先のことになります。また、すべての企業でこれだけの高度化したRPAが必要かといえばそうではありません。なぜなら、高度化したRPAではプログラマーが必須となるうえ、導入コストも大幅に上がってしまうからです。
もちろん、それだけのコストを払ってでもそうした機能を求める企業もあるでしょう。ただ、多くの企業にとってはクラス1のRPAでも業務効率化、生産性向上に大きく貢献します。
これからの時代に選ばれるRPAは、クラス1であってもより高機能かつ使い勝手のよいRPAです。今以上に簡単にロボットを作成できる、既存システムとの連携がより自由に行えるようになるなど、できるだけプログラマーの力を借りずに目的を達成できるRPAが求められるようになるでしょう。
RPAを導入すべき理由
デジタルトランスフォーメーションを実現するにはさまざまな方法がありますが、なぜRPAがDXの推進において有用とされているのでしょうか。ここでは、数ある手段の中でもRPAを導入すべきその理由について順を追って解説しましょう。
DXの必要性
そもそもデジタルトランスフォーメーション(DX)とはどういった概念なのでしょうか。
経済産業省が発表した「DXガイドライン」の定義によると、DXは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。
簡単にDXを言い表すと、「ITを活用して企業組織に変革を起こすこと」で、その目的は「企業の競争の上位性を確立するため」です。デジタル技術を活用して新しい製品・サービスを展開する企業や新規参入者が次々と登場し、あらゆる分野で市場競争は日増しに激しくなっています。こうした激化する市場競争で優位性を獲得するためにDXの推進が必要とされているのです。
このように、DXは本来、デジタル改革によって競争上の優位性を確立して新しい価値を生み出し、デジタルを活用して生産性の向上につなげる革新的な取組みです。しかし、今日の日本においては「人手不足問題解決」や「2025年の崖」と呼ばれる約12兆円の経済的損失の解決手段としても注目されている状況にあります。
こうした課題の原因となっているのが「レガシーシステム」と呼ばれる複雑化・ブラックボックス化した基幹システムの存在です。レガシーシステムのマネジメントは社外ベンダーのITエンジニアに委ねられている場合がほとんどで、レガシーシステムの技術承継が難しいと回答した企業は6割を超えています。このため属人化したシステム保守・運営の技術はIT担当者の退職の時期を迎える2025年前後に喪失してしまう可能性があることが予見されています。
さらに、2020年にはWindows7のサポート終了、2025年にはERPのサポート終了もアナウンスされています。そのため、旧来の基幹システムを維持し続けることはコスト面やセキュリティ面から非常にリスクが高く、早急なシステムの刷新が求められています。
DX実現の切り札となるRPA
独自の課題を抱えている日本におけるDXですが、今回ご紹介しているRPAはDX推進の第一歩となることや、業務の中核を担うシステムであるということが徐々に認知されはじめています。
RPAは人よりも約3倍速く業務を自動処理することができ、人の手よりもはるかに正確にデータを作成することできるため、DX推進は飛躍的に効率化します。
DXはいくつかの段階を踏んで実行されます。RPAは、その初期段階における「デジタル化による業務強化と業務自動化」の領域をカバーすることが可能です。DXの推進のベースとなる「業務自動化の段階」で絶大な効果を発揮するRPAですが、DXの最初期段階の既存ビジネス資源である書類のデータベース化業務においても、DX推進の第一歩として活躍します。
また、RPAの導入・運用は多くの人的リソースが単純作業から離れることを意味しており、DXの本領である「競争上の優位性確立と新しい価値の創出」にシフトできるということです。
DX実現の切り札とも言えるRPAですが、数あるRPAの中からどういった機能を持ったものが良いのでしょうか。
RPAに求める性能としては、「IT技術が必要なく現場で作成・運用できる」ものであることが重要です。社内でRPAのルールを簡単に定義・作成できることは、レガシーシステムのようにブラックボックス化することを回避し、システムを自社の手でマネジメントすることにつながります。また、DX推進に合わせてさまざまなアプリケーションに対応できる性能を持っていることも重要なポイントです。
参考:DX実現の切り札となるRPA(RPAの導入にかかるコストとは)
RPAを軸とするDX推進に必要なこと
DX推進の手段の一つとしてRPAの導入を行うのであれば、短期集中的に導入から定着までを進めていかなければなりません。なぜなら、経済産業省が公開したDX推進のためのレポートタイトルが「2025年の崖」であるように、早急にDXを進めていかなければ、大きな損失を生んでしまうリスクがあるからです。
そこで、スピーディーにRPAの導入、定着を実施するためのポイントを2つ紹介します。
現場で工夫して負荷軽減を進めるカルチャーの創出
RPAの導入を進めていくための方法は、経営層主導によって進めていく方法、そして現場が主体となって進めていく方法の二つに分けられます。
一般的に、より迅速かつ全社的にスケールさせていくのに適しているのは、経営層が主導となって進めていく方法です。特に大きな成果を出すためには、トップダウンのほうが社内制度の改正や内部統制ルールの整備をスムーズに進められるでしょう。
ただし、トップダウンで迅速な導入・定着を進めていくためには一つ条件があります。それは、経営層が現場の課題や業務のボトルネックをしっかりと把握していることです。経営層が現場の業務を把握していないと、何から手をつけるべきか、どの業務の自動化を進めていけばよいかがわからず、かえって時間がかかってしまうでしょう。
トップダウンで進めつつ、迅速にRPAを定着させていくためには、経営層が現場のリーダーをまとめ、意見を集約したうえで大枠をまとめ、あとは現場主体で回していけるようにすることです。
上からの指示に従うだけでなく、現場でもそれぞれが工夫を凝らして業務の負荷を軽減していく、というようなカルチャーをいかにつくれるかがポイントとなります。もちろん、そのためには現場の社員もRPAを理解し、どうすれば業務効率化を進められるかについてしっかり学習していく必要があるでしょう。
業務そのものを最適化する
これまで、多くの企業では部門ごとにシステムを導入し、それぞれの業務で最適化を行うのが一般的でした。いわゆる部分最適化ですが、DXを推進していくためには企業のあらゆるデータを資産とし、部署ごとに最適化されたシステム内データの集約・分析の実現、つまり全体最適化の思考を持つ必要があります。
そのうえでコアな業務とノンコアな業務の切り分けを行い、コア業務に集中できる環境をつくるためにノンコア業務へのRPA導入を進めていくのです。
「最低化思考」と「業務の切り分け」。DX推進の肝となるこの2つを全社的に浸透していけるよう社員の育成を行い、改革を進めることが重要だといえるでしょう。
まとめ
今回は、RPAの今後について市場データを基に解説しました。RPAは2020年現在「幻滅期」にありますが、高い成長市場にあるRPAは今後もさまざまな機能を持ったものや、関連サービスが登場するでしょう。したがって、今後はゆるやかに現実的なレベルで適用が進むものと予想できます。
これからの日本企業のDX推進に求められる「エンジニアに依存しないITの活用」を具現化するRPAが「ロボパットDX」です。「ロボパットDX」は、「事業部門が自分で自動化できるRPA」という考え方のもと、現場の業務フローと必要な機能を追求し、改善を重ねてきました。DXを推進している多くの企業でご利用いただいます。現在、RPAの導入・運用やDXの推進でお悩みの方は、ぜひ当社FCEプロセス&テクノロジーまでご相談ください。
https://fce-pat.co.jp/concept/