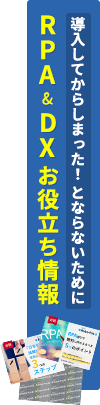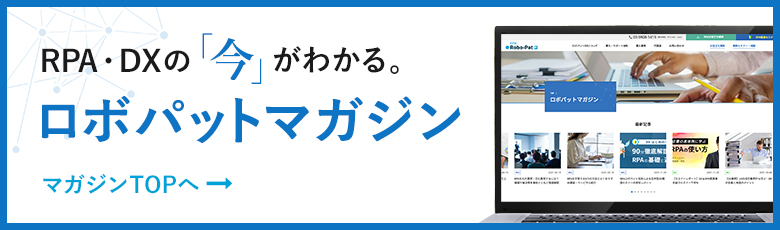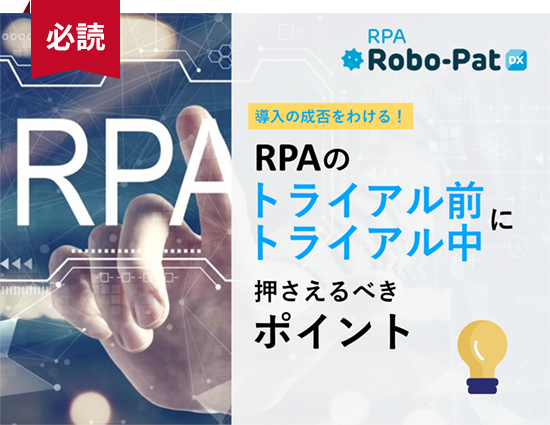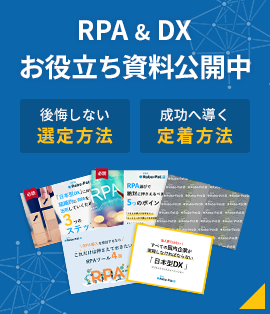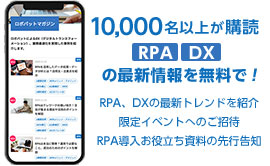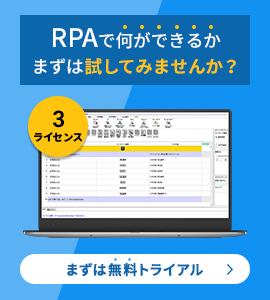業務改善に効果的な「RPA」とは?
「RPA(Robotic Process Automation)」は、働き方改革や生産性向上を支えるツールです。
RPAが注目されるようになった背景には、導入効果の高さがあります。これまで手作業で行っていた事務作業をRPAが自動処理することにより、作業時間と工数の大幅な削減が可能になりました。
事務作業の種類はさまざまですが、現在のRPAが対象とするのは主に定型化されたルーチンワークです。たとえば、ECサイトの売り上げデータの入力や、集計したデータの変換などの業務と相性が良いとされています。
オフィスの事務作業を大幅に効率化させる効果があることから、日本でもRPAを導入する企業が急増しています。
RPA導入のメリット
RPAを導入すると、人件費の削減と生産性の向上など、企業活動にとって大きなメリットが得られます。
人件費の削減につながる
RPAの導入により、これまで手作業で行っていた作業を自動化できるので、人件費を削減できます。企業経営において、経費の大半を占めるのが人件費。元々、RPAが担当するルーチンワークは時間と工数がかかるので、必要な人件費は決して少なくありません。もちろん、RPAシステム自体のコストはかかりますが、長期的な観点で考えれば、人件費削減の効果は非常に大きいといえるでしょう。
サービスの向上を目指せる
RPAを導入すれば、サービスの品質と速度の向上が図れます。RPAは、作業プロセスを設定すれば、その内容どおりの作業を繰り返してくれます。ルーチンワークは、手作業よりRPAのほうが高速かつ正確に行えるため、顧客に正確なサービスをより短時間で提供できるようになります。結果的に顧客満足度が上がり、事業拡大もスムーズに進めやすくなるでしょう。
作業ミスによる損失を防ぐ
RPAの導入により、作業ミスによる損失を防ぎやすくなります。どれだけ注意していても、手作業ではどうしてもミスが出てしまいます。作業ミスは業務の停滞のみならず、顧客満足度の低下にもつながりかねないため、可能な限り減らしたいものです。RPAなら、所定の手順に従って正確な作業ができるので、ヒューマンエラーによる作業ミスと損失を防げます。
生産性がアップする
RPAを導入すると、企業の生産性の大幅な向上が見込めます。RPAは、処理スピードと正確性が高いうえに、基本的には24時間365日連続で稼働できるため、膨大な業務を正確に処理できます。さらに、RPAの導入で浮いたリソースを、ほかの業務に割り当てることができることも魅力です。単純作業はRPAに任せ、クリエイティブな業務を人間が行うことで、より付加価値の高い商品・サービスを提供できます。
RPA導入のデメリット
RPAの導入時は、イニシャルコスト・ランニングコストの負担が生じることや、作業のルール化や引き継ぎに手間がかかることに注意が必要です。
導入コストが負担になる
RPAは高度なITシステムなので、導入には一定のコストがかかります。RPAの種類によっては、初期費用だけではなく、継続利用するためのライセンス契約や、メンテナンスを受けるための費用なども必要な場合があるので、事前にしっかりコストシミュレーションを行っておきましょう。
業務が止まる可能性がある
RPAは基本的には連続稼働できますが、まれにシステム障害やエラーなどで停止してしまうことがあります。エラーが絶対に起きないというシステムは存在しないので、万が一のときのことを考えて、サポートやメンテナンス体制が万全な製品を選ぶことが重要です。
間違いに気づけない可能性がある
RPAが行えるのは、あらかじめ設定したルールに基づく作業です。しかし、そのルール設定に誤りがある場合は、人間が停止させるまで不正確な作業を続けてしまいます。RPAは設定した作業を正確に行えますが、その作業内容自体が正しいかどうかは判断できません。そのため、RPAを稼働させる前に、設定した内容が正確かどうか検証する必要があります。
引き継ぎをする際に注意が必要
RPAの運用担当者が変わる場合は、作業内容や手順のルールを後任者に引き継ぐ必要があります。RPAは設定した内容を自動的に行えますが、担当者がその内容を理解していなければ、RPAの運用が属人化・ブラックボックス化してしまいます。作業内容や手順に変更が生じたときに、担当者が適切に対応できるようにするために、正確な引き継ぎができる体制を構築しましょう。
業務改善目的でRPAを使うための事前準備
業務改善目的でRPAを導入するときは、事前に目的を明確化しておき、業務内容を見直してRPAに移行しやすい環境を整備しておく必要があります。
業務改善で求める成果を明確にする
RPAで業務改善を目指す場合、求める成果を明確化しておきましょう。
従来の業務改善手法では、人事・経理・財務・営業・調達など、人手が必要になるルーチン業務は検討対象から外れていました。しかし、RPAはこれらの業務も改善できるので、「生産性向上」「従業員の負担軽減」「リソース配分の効率化」など、ゴールを明確化しておきましょう。
業務そのものを見直す
RPAで業務改善をするにあたり、既存の業務を仕分けして、業務内容を見直してみましょう。
人手による作業が多く、RPAでデジタル化することにより効果が大きい業務
このような業務は、RPAではなく、Excelなど従来の業務ソフトでも自動化できるケースがあります。
異なるシステムやアプリケーションからデータや情報を集め、編集や集計などをおこなう業務
RPAが得意とする分野なので、RPAの導入によって大きな効果を得られます。
同様の処理を多くの人もおこなうことで、処理ルールが徹底されず後工程での確認や修正に手間がかかる業務
この場合は処理の自動化によるリソースの節約効果よりも、業務品質の向上効果を狙うほうが良いでしょう。
処理条件が複雑なものや頻繁に変更する業務
処理条件が複雑、もしくは変更頻度が高い場合は、手作業では混乱することがあります。このような業務は、RPAで自動化するとミスを予防でき、品質と生産性が飛躍的に高まるでしょう。
業務処理の際の品質管理が厳しく求められている業務
入力業務や編集処理後の品質管理は、手作業で行うと見落としが発生やすい工程です。そこでRPAを導入することで、より正確な品質管理が行えるようになります。
異なるシステム間やデータ間の追加・削除やバージョンの整合性などを保証したい業務
RPAは正確な作業ができるので、システム間・データ間の不整合によるトラブルの防止に役立ちます。
そのほかにも、作業の分量・順序・担当部門などが社内で「暗黙知」になっている場合は、曖昧な部分をなくしておくことも重要です。
業務の流れを正確に把握する
RPAを導入して業務を改善するためには、業務の流れを正確に把握しておく必要があります。
1.導入準備
RPAで改善する業務を選定し、目的の明確化や現状把握、目標設定、開始と終了の条件設定などを行います。
2.業務の棚卸しと流れの設計
対象業務に関する作業を洗い出し、RPAを組み込んだ流れを設計します。
3.フローチャートの作成
業務の流れを記したフローチャートを作成し、開始から終了までの流れを記します。
4.判断基準や異常処置の設計
明確な判断基準を作成して、異常処置まで洗い出します。
5.RPAの作業と人の作業を明確化する
RPAに任せる作業内容と、人間が担当する業務を明確に分けます。
6.効果と改善の確認
RPA導入の効果を確認して、それに基づいて業務改善を行います。
7.書類の整備
新しく作成した仕事方法に沿って、書類の作成や改訂を行います。
RPAを導入し業務改善を成功させるには?
RPAを導入して業務改善を成功させるためには、適切な運用体制を構築することや、業務改善の効果を定量化しておくことが重要です。
RPAの管理・運用体制を構築する
RPAは指定した動作を正確に行えますが、運用担当者がきちんと管理しなければ、管理者不在の「野良ロボット」が発生します。その結果、システムの負荷や業務工数が増大して、業務改善と正反対のことが起きる可能性があります。
そのため、RPAの導入前に運用ルール・体制をしっかり構築しておくことが重要です。また、RPAの運用管理チームを設置して、ロボットの品質管理を徹底するのも良いでしょう。
制定しておきたい運用ルールは以下4つです。
ロボット作成時の申請方法
自動化させたい業務内容について、システム部門などRPAを管理している部門に伝え、ロボット作成を申請するための連絡フォーマットを作成します。
ロボットを作成できる社員の資格
RPAのロボットを作成するために必要なスキルを洗い出し、社内資格や満たすべき条件などを策定します。
ロボット作成のためのスキルアップ方法
RPAのロボット作成の社内資格を得るために必要な、教育コンテンツの受講方法などを社内に周知します。
RPAを運用しているときにトラブルが発生した場合の対応方法
RPAの運用部門だけでは解決できないトラブルが発生したときのために、対処法や相談先などをまとめておきます。
また、すでに存在する「IT統制ルール」の中に、「RPAのロボット開発ルール」を組み込むことも重要です。利用するRPAツールの詳細についても、「RPAのロボット開発ルール」に記載して社内で共有しましょう。
現場社員から見た「開発されたRPAのロボット」の品質レビューもあると、業務改善に役立てることができます。
現場主体で運用する
日本企業の多くは、社内エンジニアがいない傾向があります。しかし、RPAはエンジニアが不要なツールも多いので、現場主体での運用体制を構築しやすいでしょう。この場合、RPAによる業務改善は「システムアプローチ」ではなく、「現場アプローチ」で考えることが重要です。
このように運用すると、RPAを活用する現場部門にノウハウが蓄積していきます。「RPAに任せる業務」と「人に任せる業務」についても、現場部門で適切に判断していけるようになるでしょう。
業務改善効果を定量化する
RPAの導入目標の達成状況を評価するために、改善状況を数値化することも大切です。誰が見ても導入効果がわかりやすくなり、どの業務にRPAを利用したら良いかを判断するための指標にもなります。
RPAの導入事例
RPAツール「ロボパットDX」の導入事例を、業種・業界別に6例ご紹介します。
外食・店舗運営・小売業
株式会社ビープラウド様は、全国に展開する淡路島カレーのライセンス本部や、デリバリー業態を運営しています。同社は新規業務にRPA「ロボパット」を導入し、自動化を進めることにしました。
ECサイトの受注や在庫管理、集計業務などのような、担当者のスキルによって時間対効果が異なる業務において、とくに高い導入効果が出ています。ロボパットは、インターフェースがアイコン画像で構成されているので、誰でも簡単に扱えることも魅力です。
モチベーションが上がりにくい単純作業をRPA化することにより、従業員のモチベーションが高まり、他業務・既存業務の効率も高まりました。結果的に「新しいこと」に対する抵抗感が薄れ、企業風土までもが改善されたとのことです。
株式会社ビープラウド様のRPA導入事例については、以下の記事で詳しく解説しているのでご参考ください。
株式会社ビープラウド|RPA-Robo-PatDX(ロボパットDX)
税務・会計に関する相談、支援事業
株式会社エーエスシー様は、税務申告・会計事務など、企業の税務に関するサポートを提供しています。同社では、税務まわりの細かくて工数のかかる作業を自動化するために、RPA「ロボパット」を導入しました。
RPAの導入効果を高めるために、同社は「どんな業務を自動化するか」「どんなロボットを作るか」などのアイデアを出し合いました。さらに、組織全体にRPAを浸透させるため、煩雑な電子申告業務を自動化するロボットを作成し、実際に試してもらいました。こうした取り組みの結果、ほぼ全員がRPAを活用するようになり、高い導入効果が得られています。
株式会社エーエスシー様のRPA導入事例については、以下の記事で詳しく解説しているのでご参考ください。
税理士法人ASC/株式会社エーエスシー|RPA-Robo-PatDX(ロボパットDX)
インターネットサービス開発/カスタマーサクセス
株式会社POPER様は、校務支援クラウドサービス「Comiru」を展開しています。同社は単純作業を自動化して、より付加価値の高い業務に注力するため、RPA「ロボパット」を導入しました。
これまでは、自社サービスの利用状況の集計に、1日3時間もの工数がかかっていました。しかし、RPAを導入して単純作業をRPAに任せることで、解説動画の作成のような「やりたくても時間がなくて手をつけられない」タスクに取り組めるようになりました。ロボットの作成時も、自身で行っている作業を細分化し、その手順をシナリオとして組み立てればOKなので、簡単に使いこなせることが魅力です。
株式会社POPER様のRPA導入事例については、以下の記事で詳しく解説しているのでご参考ください。
株式会社POPER|RPA-Robo-PatDX(ロボパットDX)
インテリア商品のEC事業
株式会社アイズコーポレーション様は、インテリア商品のECモール事業を展開しています。同社はルーティーン業務を自動化し、より重要な売上創出や新商品の企画に注力するために、RPA「ロボパット」を導入しました。
とくに大きな課題だったのが、各モールに行う出荷報告の業務。注文当日に行う必要がありますが、外部倉庫を使用している場合は翌日に遅れてしまうこともありました。出荷報告の遅延は販売機会の損失にもつながります。RPAの導入により、出荷報告はもちろん、売上・アクセス数・転換率などの確認の自動化にも成功し、年間で949時間ものEC業務を削減できました。
株式会社アイズコーポレーション様のRPA導入事例については、以下の記事で詳しく解説しているのでご参考ください。
株式会社アイズコーポレーション|RPA-Robo-PatDX(ロボパットDX)
インターネットメディア運営事業
株式会社リブセンス様は、インターネットメディア関連の事業を展開しています。同社は各部署のルーチンワークを自動化し、より付加価値の高い業務を進めるために、RPA「ロボパット」を導入しました。
ロボパットの「誰でも操作できる」という利点を活かし、「誰でも編集できる」ロボット作りを意識したのが、同社のRPA運用の特徴です。社内の複数のチームでロボットを作成し、全体で1か月あたりに約50時間、営業日換算で約6日分の効率化を実現できました。年間だと72営業日分に相当するので、極めて大きな導入効果だといえるでしょう。
株式会社リブセンス様のRPA導入事例については、以下の記事で詳しく解説しているのでご参考ください。
株式会社リブセンス|RPA-Robo-PatDX(ロボパットDX)
採用支援事業、地域創生事業
株式会社シンミドウ様は、採用支援事業・地域創生事業を展開しています。同社は業務効率を改善し、支援事業により注力できるようにするために、RPA「ロボパット」を導入しました。
同社がまず作成したのは、採用支援事業におけるWeb検索やメール送信作業を自動化するロボットです。以前はマクロを組んで自動化していましたが、すぐにエラーが出て止まってしまうため、業務負担の軽減効果はほとんど得られませんでした。RPAの導入により、さまざま業務の効率化が進み、支援先に対するサービス向上に今まで以上に注力できるようになりました。
株式会社シンミドウ様のRPA導入事例については、以下の記事で詳しく解説しているのでご参考ください。
株式会社シンミドウ|RPA-Robo-PatDX(ロボパットDX)
まとめ
本記事では、RPAの導入で得られるメリットや、業務改善を成功させるためのコツをご紹介しました。
市場調査会社のMM総研による動向調査によると、企業におけるRPAの導入率は2018年では22%、2019年では38%と確実に増加傾向にあります。大手企業に絞ると、2019年11月時点で50%以上と高い数値になっています。
また、RPAを導入した企業の80%が「今後は利用を拡大することを検討する」と答えています。これらの数字からわかるとおり、将来的に見てもRPAを導入する企業はますます増えていくと予想されます。
RPAの導入にあたっては本記事で紹介した内容を理解したうえで、導入事例などを参考にしながらRPAツールを比較検討しましょう。
「ロボパットDX」は、充実した導入・運用サポート体制が無料で受けられるRPAツールです。1カ月無料で3ライセンスのトライアルもありますので、RPAの導入を検討中の担当者の方は、ぜひこちらからロボパットDXの詳細をご確認ください。